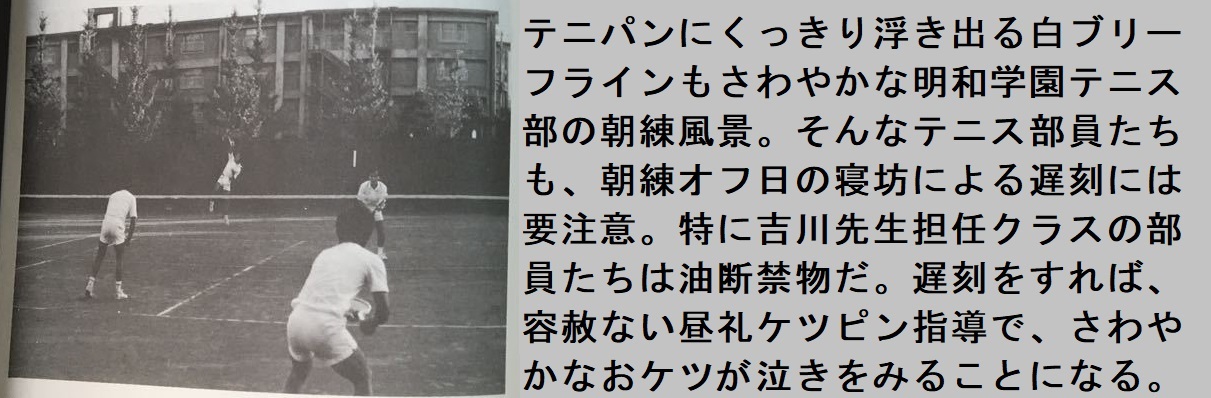
S大南寮 目蒲君スペシャル スピンオフ 津島先生回顧録 我が母校 明和学園
南寮編・目次に戻る / 南寮編・スピンオフの目次に戻る
第二章 ダビデの頃
1 第一美術室・放課後掃除の件
東京都中野区にある中高6年一貫制男子校、明和学園・中高等部は、明治時代に設立された旧制・明和中学がその前身であるが、その敷地は奇跡的に戦災から免れたこともあり、昭和30年代においても、戦前のままの校舎を受け継いで使用することできた。そのため、最新ではなかったものの、学校設備は充実していた。
明和学園の敷地内、正門からみて体育館棟(屋内運動場)のさらに奥にあるのが、木造2階建ての芸術科校舎だった。その校舎には、図画工作室、美術室、音楽室がそれぞれ2教室ずつと、それらに付属する各準備室と芸術科職員室が備えられている。
それらの芸術科関連の各教室を、理科各科の実験室とあわせて、明和学園では「特別教室」と呼ぶのだが、その特別教室の放課後の掃除は、中2・中3の生徒たちの役割だった。中2・中3それぞれAからEの1学年各5組に所属する、総勢約500名の生徒らが、5〜6人を1つの班として、特別教室の掃除当番を一週間単位でシフトを組んでつとめるのである。
一般に、中2・中3の生徒にとって、「特別教室」の掃除は「楽勝もの」だった。通常の教室に比べると使用頻度が少ない教室も多く、また、それらの教室で授業・実験・実習が行われた場合は、終了時に、その教室を使用した生徒たちが「軽く」掃除をしていくことが、教師たちによって指導され、習慣化しており、自分たちのホームルームほどは汚れてはいなかったからだ。
しかし、そんな「楽勝もの」の当番であっても、特別教室の掃除をまじめなクラスメートに押しつけて怠ける、やんちゃで要領のいい生徒も少なくなかったのである。
・・・・・・・・・・・
1959年(昭和34年)6月。その月の第1週の第一美術室の放課後掃除は、2年B組の第4班の担当だった。
月曜日。それは、2B・第4班が担当する第一美術室の放課後掃除の第一日目であった。2B4班のメンバーといえば、出席番号順に、田中義人君、塚田和博君、津島裕二君、手塚勝君、寺田義之君の5人。
第一美術室は、通称、「デッサン室」とも呼ばれていて、主に高校生の美術の時間に利用されており、中2の津島君たちが入室するのは、その日が初めてであった。
「うわぁ!く、くせぇ・・・窓、全部開けようぜ・・・」
第一美術室に一番で乗り込んできた津島裕二君が、鼻をヒクヒク動かしながら、後から入ってきたクラスメート4人に命令するように言うのだった。その教室は、しばらく使われていなかったのか、絵具の臭いとともに、カビ臭さ、ムッとするような生暖かさ、そして、篭って沈殿したような重い空気にみたされていた。
「おお!」
他の4人もそれに同意したのか、教室の窓を手分けして開け始める。そして、廊下側の窓も、2か所ある教室の入口もすべて開けていく。ほどなく、教室に、新鮮な空気が流れはじめ、そこに満たされていた重くじっとりとした湿った空気も追い出されていくのだった。
ホッと一息ついた津島君が、好奇心に満ちた目で、その教室をグルっと見回す。そして何かを思いついたのか、顔に笑みを浮かべて、「よし・・・」とつぶやくのだった。
その日の第一美術室は、やけにガランとした何もない教室だった。デッサンに最低限必要なはずの椅子やイーゼル(画架)も片付けられおり、壁に掲げれらた複製画や貼り付けられた美術史の年表がなければ、黒板と教壇・教卓がある通常の教室にしかみえなかった。
津島裕二君は、ニヤニヤしながら、他の4人に言うのだった。
「なあ、この教室の掃除さ・・・3人いれば十分じゃねーか?交代でさぼって楽(らく)しねーか?」
「ああ、オレもいまそう思った。」
津島君に早速同意するのは、田中義人君。やはりニヤニヤと笑っている。真っ黒に日焼けした顔に、笑った時にみえる健康そうな白い歯が印象的な野球部員。2Bでは、津島君と肩をならべるやんちゃ坊主だった。田中君はすでに野球部の練習用ユニフォームに着替えており、教室後方にある用具箱から、ホウキを一本取り出してきて、掃除を始める前からもう掃除は飽きたとばかりに、そのホウキを野球のバットにみたて、素振りの練習もどきを始めている。
「楽勝もの」と言われる特別教室の掃除であっても、なんとか怠けようとする、それが思春期男子というものなのかもしれない。
「おまえらは、どうなんだよ!?」
ちょっと戸惑った顔つきをしている手塚勝君と寺田義之君に、田中君が、やや意地の悪い笑みを浮かべて問いかけるのだった。
「ま、まあ、そう思うけどさ・・・イエローカードにバレたら、やばくねーか?」
「そうそう、今日の昼のSTでもさ、なんかアイツやけにはりきっちゃって、
『おまえら、オリンピック、オリンピックって浮かれてばかりいるんじゃねーぞ!オリンピックはまだ5年先だからな!
オリンピックが東京に決まったことを記念して、今月はみんなでまじめに掃除に取り組む月とする!
掃除さぼりやがったら、罰当番だけでじゃすまねーぞ!サボったヤツのケツには、翌日、オリンピックじゃなくて、ケツピンピックだ!!
運動会も終わったからな、 今月からいよいよ、この俺の黄色いムチも、本格始動だ!ビシッ!ビシッ!と1年の時よりも容赦なくおまえらのケツに飛ばしていくから、さぼったヤツは覚悟しとけ!』
とかいってたじゃん・・・」
手塚君の「イエローカード」のものまねに、津島君たちは大笑いをする。
「ケツピンピックってなんだよ!いみねぇー!」と寺田君。
「す、すごい・・・て、手塚君、昼のSTで先生が言ったこと、全部おぼえてる・・・やっぱり、手塚君、あたまいいんだ・・・」
一方、塚田君はそう思いながら、手塚君に尊敬のまなざしを向ける。
オリンピックといえば、前月下旬、すなわちその年の5月26日に、西ドイツのミュンヘンで開催された第55次IOC総会において、「東京」が1964年開催予定の第18回オリンピック競技大会(夏季大会)の開催地に選出されていたのだ。
「オレ、あんとき、わからなかったんだけどさー、オリンピックと掃除がどう関係してるんだ?」と田中君。
「知るかよ・・・そんなの・・・でも、イエローカードがケツピンだっていえば、さぼりがバレると、パンツ一丁のケツ、あの黄色い棒でビシッってことだろ・・・」と手塚君。
「ケツピンピックだ!!ビシッ!!」と寺田君が笑いながら言う。
イエローカードとは、津島君たちのクラスである2年B組の担任教諭で体育担当の吉川進(よしかわ すすむ)先生(28歳)のことだった。
明和学園では、中1から高3まで、毎年、クラス替えがある。
そのクラス替えで、津島君は、1年生の時と同じB組であった。しかも、それは単なる偶然だったのか、はたまた、裏でなにか教育的措置がとられたのか、津島君の2年生でのクラスの担任は、中1のときと同じ、体育担当の吉川進先生だったのである。
もちろん、同じB組でも、中1の時とくらべてクラスの面子はかなり入れ替わっていた。そして、津島君と同じ2Bには、なぜか、運動部所属のやんちゃ坊主の生徒たちが、ケツ、もとい、顔を揃えていたのである。これには生徒たちも、裏で何かある!と思わずにはいられなかったのだ。
津島君が何を思ったのか、穿いていたサッカーパンツを膝までおろすと、黒板に両手をつくような体勢をまねて、白ブリーフのプリッとしたケツを後ろに突き出す。そして、
「ィーッス!お世話になります!」
と、デカい声で言うのだった。
ニヤリと笑った田中君が、手に持っていたホウキで、タイミングよく、津島君の白ブリーフ一丁のケツを叩くしぐさをする。
「バッシ〜ン!」
「シタ!お世話になりました!」
津島君と田中君の、「即興ケツピン寸劇」に、手塚君と寺田君は、やや引き気味ながら、苦笑いをしている。
「『お世話になります!』とか『お世話になりました!』とか挨拶させるのさぁ、いい加減、やめてほしいよな・・・」
と手塚君がつぶやく。
手塚君と寺田君の表情を観察しながら、田中君が、
「おまえら、ケツピンくらいでなにビクビクしてんだよ!」
と言い放つ。
やんちゃ坊主からしてみれば、「掃除さぼって、ケツピンの一発や二発、たいしたことねーぞ」って算段か。先生からサボるなといわれれば、なおさらサボりたくなる、そういう年頃なのかもしれない。
「ビクビクしてねーけどさ・・・やっぱりケツ痛いのいやだし・・・それにさぁ・・・オレたち、もうガキじゃねーんだから、中2にもなってパンツ一丁でケツ叩かれるとか、すげー恥ずかしくねーか?」
そう言う手塚勝君は、ポッと頬を赤らめる。
手塚君は、野球部の田中君同様によく日焼けしているテニス部員。スポーツ刈りもお似合いの、いかにも育ちがよさそうな顔をした、イケメン君である。部活に備えてか、すでに、白のテニスパンツに着替えており、そのテニスパンツから透けて見える、スクールパンツである白ブリーフのラインも鮮やかでさわやかだった。
2 昼礼ケツピン
そんなさわやかな手塚君も、昨年度、中1の3学期に一度だけだが、テニス部の朝練オフ日に寝坊して始業に遅刻し、校門で生徒証を取り上げられ、昼のSTで、その生徒証を返却してもらうのとひきかえに、吉川先生のケツピン棒のお世話になったことがあった。
吉川先生のクラス限定の名物である昼のST時のケツピン指導、通称、「昼礼ケツピン」であった。遅刻者に対する扱いは、各担任に任される中、吉川先生は、昼のST(昼礼)の際に、正当な理由のない遅刻者に対して、ケツピン指導を敢行していたのだ。
それまで、吉川先生の黄色いムチがクラスメートたちのパンツ一丁のケツにビシッ!と飛んでいく様子を何度も目撃していた手塚君だった。しかし、そのムチ先に自分自身のケツを出すのはその日が初めて。午前中の授業には全く集中できず、昼飯の時間が来るのが憂鬱だった。
「よし!今朝、遅刻したヤツは、前に出てこい!生徒証を返してやる!」
竹棒に黄色いビニールテープをグルグルと巻いたケツピン棒を持った担任の吉川先生が、そう宣言すると、クラスからドッと笑いが起こる。その日の吉川先生は、体育の授業でのいでたちそのままに、白の半袖体操着に、下は白の体育トレパン(トレーニングパンツ)だった。
「は、はい・・・」
それは、吉川先生のクラスの昼のSTでの名物行事、名物儀式だった。
カチャ、カチャ、カチャ・・・
手塚君は、言い訳をしても無駄だと観念しているのか、元気なく返事をすると、学ランズボンのベルトを緩めて、ズボンを脱ぐ。そして、学ラン上着も脱いで、それらを自分の椅子の背に几帳面にかけるのだった。
吉川先生のクラスでは、ケツピン指導を受ける時はパンツ一丁がお約束。ズボンは自分の机のところで脱いで、前に進み、教壇に上がらなければならない。
そんな手塚君の、覚悟を決めるも、白ランニングシャツに白ブリーフ、そしてその上にYシャツを着ただけの、ちょっと情けのない姿を、ニヤニヤ顔で眺めるクラスメートもいれば、そんなことは気にもせず、すでに空腹を我慢できず、弁当に食らいついているヤツもいた。それが男子校の昼飯時というものだった。
「ヒュヒュー!マサル!パンツ一丁、色っぽいぞ!」とからかうヤツもいる。一方、「マサル!ガンバレ!」と励ますものもいた。
そんなクラスがざわつく中、真っ赤な顔の手塚君は、一人トボトボと、下を向いたまま、クラスメートの机の間を黒板の方に歩いていく。クラスメートの机の上には、すでにおいしそうな弁当がひろげられている。いつもは気にもならない、あたりにただよう弁当のおいしそうな匂いも、その日の手塚君にはうらめしかった。
「チェッ!今日は、オレ、一人かよ・・・」
そんなことを思いながら、手塚君は、吉川先生が己の生徒証とケツピン棒を持って待ち構えている教壇の方へ向かう。Yシャツの裾の間からは、チラチラと、「1B 手塚」とフロント部分に黒マジックで描かれたスクールパンツの白ブリーフが見え隠れする。育ちがよく、スクールブリーフの洗濯と取り替えもこまめなのか、手塚君の白ブリーフは、きれいな白で、黒マジックで「1B 手塚」とブリーフの白地の上に描かれた文字が、むしろやや薄くなりつつあった。
下はパンツ一丁のまま、真っ赤な顔で教壇に上がってきた手塚君のその姿をみて、吉川先生は、よく日焼けした顔から健康そうな白い歯をみせて、ニヤニヤ笑っている。
「手塚!潔くパンツ一丁で来ってことは、遅刻の理由を聞く必要はないようだな。」
吉川先生は、自身のトレードマークでもある黄色いケツピン棒の両端を両手で握るようにして持つと、両腕を万歳するかのように挙げて、上体を左右に傾けたり、また身体の向きを変えて、ケツピン棒を持った両手は挙げたまま、上体を前に屈めたり、後ろに反らしたりして、まるでケツピン指導前の「準備運動」をするかのようなしぐさをするのだった。
それをみていたクラスからは、笑いとともに、「おー」とか、「イエローカード、はりきっている・・・」とかの声が上がる。その声に、自分の弁当箱に顔をうずめていた生徒たちも、思わず顔を上げ、ニヤニヤする。
そんなクラスの反応に応えるかのように、吉川先生は、さらにニヤニヤしながら、今度は、そのケツピン棒を右手に持ちかえると、それで、ビュン!ビュン!と何度か空を切るのだった。その音を聞き、クラスメートたちの間からは、さっそく、「おー」とか「こぇー」とか「マサル!泣くなよ!」の声が上がる。
先生のその姿とクラスメートたちの反応をみて、そして、まもなく、自分のケツに飛んでくるであろう笞(ムチ)が空を切る音を聞いて、真っ赤な顔の手塚君は、
「ちくしょぉ・・・ひとのことだとおもいやがって・・・」
と思いながら、白ブリで覆われたケツペタをピクッ、ピクッと動かすのだった。そして、そんな白ブリのケツの方へ、無意識のうちに、両手のひらをもっていってしまう手塚君だった。
吉川先生のピッチリとした白の体操着には、白ランニングシャツのシルエットがクッキリと浮かび上がっている。体操着を脱がずとも、吉川先生のよく日焼けして、筋骨隆々の上体を想像することができた。そして、白の半袖からヌッとでた上腕は、筋肉が盛り上がり、太く逞しく、中1男子のケツを竹棒でぶっ叩くには、十分すぎるほどによく鍛えらていることがわかるのだった。
そんな吉川先生の方に、いまにも泣きそうな顔を向けた手塚君は、
「ね、寝坊です・・・」
と、蚊の鳴くような声で、聞かれてもいない遅刻の理由をボソッと答えるのだった。そして、緊張でいよいよ咽喉が乾いてきて、ゴクリと生唾を飲み込むのだった。
「おまえにしてはめずらしいな・・・朝、寒くて、布団から出られなかったのか?」
「は、はい・・・」
「どんなに朝が寒くても、みんな遅刻してねーぞ!この甘えん坊め!」
吉川先生のその言葉に、クラスからは再び笑いが起こり、手塚君はさらに顔を赤らめる。
「は、はい・・・す、すいません・・・」
「覚悟はできてんな!黒板に両手をついてケツを出せ!」
「おー!」「待ってました!」という歓声がクラスから上がると同時に、「お昼のショー」の始まりに、拍手をし始めるヤツもいる。
吉川先生は、拍手をして調子に乗った生徒に対して、「おまえらも前にきて、ケツを出すか?」と言わんばかりに、右手に持ったケツピン棒を生徒たちの方に向けて、それをヒュッ!ヒュッ!と振りながら、拍手をしたと思われる生徒たちをギロッと睨みつける。もちろん、拍手は、即座に止むのだった。
手塚君は、
「は、はい・・・」
と、もう消えるような声で返事をすると、真っ赤な顔のまま、唇をぎゅっとかんで悔しそうな表情をして黒板の方を向き、両足を少し開いて、いままでケツをいたわるかのように覆っていた両手をケツから離し、黒板にその両手をつく。そして、おそるおそる、そぉーと、ケツを後ろ出すのだった。
「ケツはもっとしっかり後ろに突き出すようにしろ!男だろ!」
と、初めてのケツピン指導に明らかにびくついている手塚君に、吉川先生の厳しい指示が飛ぶ。
教室からは、再び、笑いが起き、
「マサル!もっとケツ出せ!!」
とのヤジも飛ぶ。
「ち、ちくしょう・・・みんなでバカにしやがって・・・」
そう思いながらも、手塚君は、今一度、両手のひらを、黒板にピタッとしっかりつけると、いままでよりもケツを後ろにしっかりと突き出すのだった。
後ろからみると、手塚君は、灰色に少し汚れた校内用の白い上履きに、白いソックスをはいている。学校に置いてありやや汚れた上履きと、こまめに取り替えているであろうソックスとブリーフの白さが対照的であった。そして、そのソックスからスゥっと伸びる両脚。産毛がうっすらとはえた脛から、膝、そして、太もものかなり上まで、テニス部員らしく、よく日焼けしていた。
そして、太もものかなり上の方、テニスパンツの日焼け跡を境界に、そこから上は、日焼けしていない白い肌。その肌の白さは、手塚君のテニスで鍛え、プリッとしまって盛り上がったお尻へと続いている。その白さを隠すかのように、手塚君のお尻は、スクールパンツである白ブリーフの綿生地で覆われている。
これから、その白いプリッと盛り上がった尻の双丘に、吉川先生が、右手に握った竹棒、通称、ケツピン棒で、ピンク色の線を一筋、描こうとしている。遅刻した者に対するケジメの罰線(ばっせん)だ。
さらに上に目をやると、手塚君のYシャツはもう買い替え時期なのか、手塚君が黒板に両手をついて腕を伸ばすと、白のランニングシャツのラインが後ろからもクッキリとわかるほどピチピチだった。
吉川先生の指示通り、両手を前についてしっかりケツを後ろへ突き出すと、Yシャツの裾がちょうどよくめくれ上がって、そのまま、白ブリーフのケツが丸出しになる。それは、まるで「お昼の尻叩きショー」の幕が上がるかのようだった。
「もうすぐだ・・・あの棒がお尻にビシッと飛んでくる・・・どうしよう・・・」
白ブリ一丁のケツはやけにスースーして、クラスメート全員の前で晒されている丸出し感も半端ない。
手塚君は、ギュッと両眼を閉じて、吉川先生のケツピン棒が己のケツに飛んでくる、その運命的瞬間に覚悟を決めていた。後ろでクラスメートたちがガヤガヤと騒いでいるのが聞こえてくる。しかし、手塚君にとって、それは、どこか他の教室で騒いでいる雑音のようにも聞こえた。
「あぁ・・・くる・・・ケツピン棒でお尻を叩かれる・・・」
手塚君は、うっすら両目をあけてみる。前にみえるのは、黒板とそこにペタっと手ひらをついている自分の両腕。両手のひらの間に、4時間目の数学の授業にでてきた二等辺三角形ABCの「A」の文字がうっすら残っているのが見える。両方の手のひらはかなり汗をかいていることがわかる。自分の手のひらの跡が、もうベッタリと黒板についているに違いない。5時間目になってもその跡はくっきりと残っていて、5時間目を担当する先生に、からかわれるかもしれない。
「これは誰の手の跡だ?」
って、ニヤニヤ笑いながら、聞いてくる先生もいるのだ。そうしたら、またクラスは大爆笑で、自分が昼礼でケツを叩かれたことを、話のネタにされてしまう・・・。
「えっと・・・5時間目の先生は、誰だっけ?」
しかし、それをどうしても思い出せない手塚君。その時だった。
ゴツン!!
スポーツ刈りにした頭のテッペンにかなり強烈な衝撃が走る。
「いてぇ!」
と、思わず声を上げ、右手を黒板から離して、頭のてっぺんを撫でる手塚君。後ろで、クラスメートたちが笑っている。
先生の方をみると、吉川先生が、その黄色い竹棒で、手塚君の頭をコツン!と一発叩いたのである。
「挨拶はどした?この寝坊助!」
と吉川先生。
手塚君は、ハッと我に返ると同時に、これから己のケツに噛みつこうとしているケツピン棒の硬さを知るのだった。まだ頭のてっぺんがジィ〜ンと痛かった。
「すげぇかたい・・・あんなかたい棒でお尻、叩かれるなんて・・・しかも、容赦なく思いっきり・・・」
「オラ!早くしろ!いつまでたっても、昼飯、くえねーぞ!」
吉川先生の言葉に、手塚君は、再び、ギュッと両眼をつむり、
「は、はい・・・お世話になります!!」
と、思い切り叫ぶのだった。
「よし!!遅刻した罰だ!ちょっと痛てぇぞ!」
と吉川先生。
担任の吉川先生のケツピン指導にもう慣れていた1Bの生徒たちである。先生が指示するまでもなく、教室前方に座っている生徒たちは、自分たちの木製の机と椅子を、ズゥズゥーと少し後方へずらしていて、教壇と教室最前列の生徒の机の間には、先生のケツピン棒が教室最前列に座る生徒に当たらないだけの空間ができていた。
吉川先生は、手塚君の白ブリ一丁のケツの左後方に、教壇から一旦降りると、左脚だけ教壇の上にのせて、手塚君のケツに狙いを定めるようにして、右手に持った黄色いケツピン棒を後ろへ振りかざすのだった。
「おーー」
「こぇー」
吉川先生の笞(ムチ)を構える時の姿勢は、生徒たちには「手加減しねーぞ!」と言っているようにみえて、いつも生徒たちからは、なんともいえない感嘆の声があがるのだった。
右脚は教室の床につき、左脚は教壇にのせて、ケツピン棒を振り上げる吉川先生の体育トレパンの尻には、「先生もお前らと同じパンツをはいてるぞ!」と言わんばかりに、白ブリーフのラインがくっきりと浮かび上がっていた。もとより吉川先生は、ステテコパンツ世代ではあったが、学校の購買部で、高校生用のスクールパンツを購入してはいていたのだ。体育の先生だけあって、吉川先生は、それをはいたときに、股間のイチモツが収まるところにピッチリと収まる白ブリーフの方が、ステテコパンツよりも身体を動かす時は優れていることを体感していたのである。
吉川先生は、そんな白トレパンに浮かび上がるブリーフラインを生徒たちに誇らしげに見せつけながら、右手に持ったケツピン棒を、後方天井の方へ向けて、さらにグッと高く掲げるように振り上げるのだった。
「行くぞ!」
吉川先生の声が耳に飛び込んできた、せの刹那、
ブン!!
という鈍くて重そうな音とともに、後ろで、パンツ一丁のケツにスゥと風を吹きかけられたような涼しさを感じる。しかし、すぐさま、
ビシッ!!
という鋭い音が自分の後ろで響き、熱い衝撃が、手塚君のケツから脳天へと走る。吉川先生のグッと腰に力を込めて振り下ろされたケツピン棒が、手塚君の白ブリ一丁のケツに、容赦なく炸裂したのであった。
「いっ、いてぇ!!」
と悲鳴にも似た声を上げる手塚君。いままでに経験したことのないようなジリジリと焼けるような熱い衝撃を、白ブリーフで覆われた己のケツに感じる。手塚君は、思わず、黒板から両手を離し、上体をややのけぞり気味に、ブリーフ一丁のケツを必死でさするのだった。
教室からは、大爆笑が起きる。
「ちくしょー、笑らえねーよ・・・ケツが焼けるようにいてぇ・・・」
そのジリジリする焼けるような痛みは、どんなに必死にケツをさすっても、すぐには消えそうになかった。
「オラ!挨拶をまた忘れてるぞ!やり直しするか?」
と、吉川先生の厳しい声が、後ろから聞こえてくる。
手塚君は、ケツは両手で押さえたまま、あわてて、吉川先生の方を向き、
「お、お世話になりました!」
と挨拶して、ペコリと頭を下げると、伏し目がちに教壇を降りていく。ケツと同じくらい、後頭部が火照るように熱かった。
「油断しているから寝坊して遅刻するんだ!もうすぐ中2になるんだから、朝、寒いくらいで、甘ったれるな!」
後ろから吉川先生のお説教が聞こえてくる。
手塚君は、下を向いたまま、ボソッと、
「は、はい・・・」
とつぶやく。
しかし、それだけではなかった。吉川先生は、手塚君の背中に向かって、
「オラ!生徒証を忘れてるぞ!戻ってこい!」
と言うのだった。クラスからは、再び、笑いが起こる。
「あ!忘れた・・・ちくしょー、笑ってる場合じゃねーよ・・・」
そう思いながら、手塚君は、下はまだパンツ一丁のまま、くるりと向きをかえて、再び、黒板の方へ戻るのだった。
もちろん、ここで、吉川先生の差し出す生徒証を、右手でケツをさすりながら、片手の左手で受け取ったりしたら、大目玉なのであるが、そこは、さすが育ちのよい手塚君である。教壇の下までいくと、ケツをさすっていた両手は、ケツから離し、両手で、吉川先生から生徒証を受け取り、「ありがとうございました!」とペコリと頭を下げるのであった。
痛くて熱いケツピン指導と引き換えに先生から受け取った生徒証を右手に持ちながらも、左手では、すぐさま再び白ブリーフのケツを必死で揉むようにおさえる手塚君だった。
教壇から自分の席まで、こんなに遠く感じたことはなかった。途中の席に座っているクラスメート全員が、自分に視線を向けているような気がした。誰かが「マサル!ドンマイ!」と言ってくれたような気がした。しかし、手塚君には、それに応える気持ちの余裕はなく、早く自分の席に戻って、学ランのズボンをはきたいだけだった。
そのあと、どうやって学ランを着て、席に着いたのか記憶が飛んでいた。しかし、椅子に座る時、思わず「いてぇ!」と声を出してしまうほどケツが痛かったことだけは忘れられなかった。
その声を聞いて、手塚君の隣で弁当箱に顔をうずめていた、野球部の石井君が顔を上げ、手塚君の方を向いて「なぁ・・・いてぇだろう!」とでもいいたげに二ッと笑う。石井君の白い歯には、弁当の白飯の上にのせられてた海苔が黒くくっついていた。それをみて、グゥ〜〜!と、自分の腹が鳴っているのを感じた時、手塚君は、すでに、弁当がつめられたジュラルミンケースを包む白い手ぬぐいの結び目をほどこうとしていた。
「は、はやく弁当くわなきゃ・・・部活の中学生・昼ミーティングに遅れちゃう・・・」
弁当に必死で食らいついている間に、ケツに感じていたジリジリと焼けつけるような熱さも徐々にではあるがおさまってきていた。やがてケツがポカポカ、ボワーンと温かくなってくる。そして、硬い椅子の上でケツを動かすと、まだ少しチクチク痛みはするものの、ケツのつらさはさっきよりも少しはましになり、むず痒くさえなってきていた。
ケツピン指導を受けた恥ずかしもあり、上を向くこともなく、下をむいて、必死で昼飯を腹につめこむ手塚君。ケツの温かさとむず痒さに意識がいくたびに、クラスみんなの前で自分だけケツを叩かれた悔しさが胸にこみ上げてきて、目頭が熱くなる。
「なくなよ・・・恥のうわぬりだろ・・・グスン・・・」
そう自分に言い聞かせながら、手塚君は、必死で、飯を腹につめこんでいく。おふくろさんがジュラルミンの弁当箱につめてくれた白飯が、その日はやけに塩辛かった・・・。
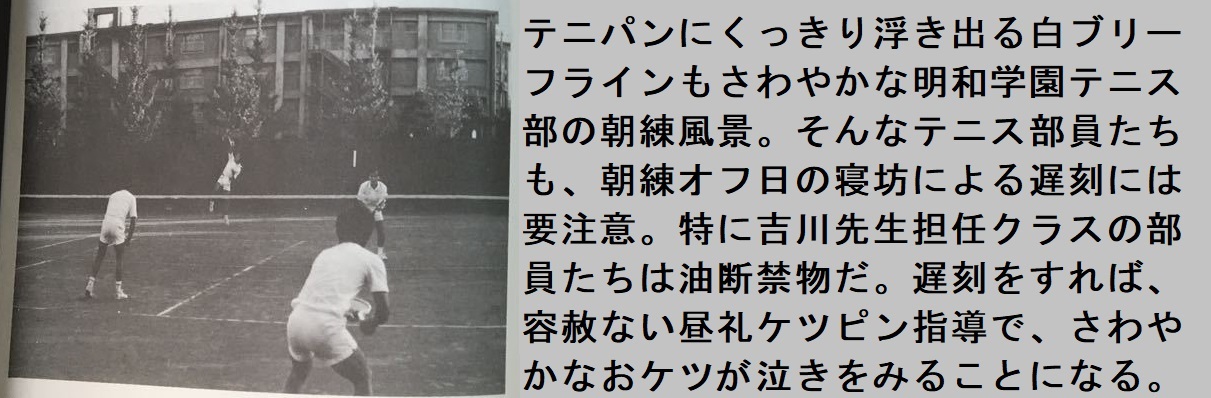
3 リーダーはつらいよ・・・
放課後の第一美術室で、2B4班の手塚勝君は、中1・3学期の昼礼で、吉川先生から初めてケツピン指導を受けた時のことを思い出している。
ケツピン棒がケツに炸裂した時の、ケツに染み入るような、ジリジリとするあの熱い衝撃。
「いままででも十分いてぇーよ・・・『いままでより容赦なく』とか、ほんと、どうなるんだよ・・・こぇーよ・・・」
と思いながら、手塚君は、右手で、テニスパンツのブリーフラインのあたりを無意識に撫でている。
手塚君は、あの時のケツの痛さと恥ずかしさを決して忘れることができなかった。
そして、今度、掃除さぼりが吉川先生にバレて、クラス全員の好奇の目に晒されながら、再び、ケツピン指導のため、黒板に両手をつかされ、パンツ一丁のケツを後ろに突き出している自分の恥ずかしい姿をすでに想像しているのか、もう耳まで真っ赤になっていた。
「チェッ、だからテニス部とバレー部は軟弱なんだよな!」
と、野球部の田中君。
そんな田中君の挑発的なもの言いに、バレー部の寺田君が色をなし、
「なんだと!バレー部は軟弱じゃねーぞ!オリンピックの新競技にだってなるんだからな!」
と言う。色白の寺田君の顔は、憤慨しているようで、耳まで真っ赤になっていた。
寺田義之君は、2B・4班5人の中では一番の長身でやや色白のバレーボール部員。その日は部活の練習が休みだったのか、明和学園の制服である黒の詰襟学ラン姿。襟のホックと第一ボタンをはずしていて、色白ながら少し赤く日焼けした胸がはだけてみえている。制服のYシャツの下は、学校指定の白のランニングシャツを着用していることが容易に想像できた。
1964年に東京で開催予定の第18回オリンピック競技大会(夏季大会)より、柔道とともに、男子バレーボールが新競技に加わることが決まっていた。もちろん、明和学園から将来のオリンピック代表選手が生まれる可能性は非常に低いが、バレーボール部員と柔道部員は、中学生から高校生まで、オリンピックのことでまだ興奮冷めやらぬ状況だったのである。
まだまだ「掃除さぼり」を躊躇するような表情をみせている手塚君と寺田君に、田中君は、
「バレなきゃいいんだよ!バレなきゃさ、ケツピンはなしだから、安心しろ!」
と言って、最後の一押しを試みる。しかし、それでも、煮え切らないような表情をみせる手塚君と寺田君。
ついに、田中君は、そんな二人にはかまってはいられないとばかりに、津島君の方を向き、
「裕二!早く、今日は誰がサボるのか、決めようぜ!」
と、掃除サボり話を、既成事実化してしまおうとするのだった。
そんな田中君に、手塚君も寺田君も呆れた表情で津島君の方に視線を向ける。3人の視線を感じながら、ちょっと考えていた津島君は、
「ハカセ、おまえはどうする?」
と、2B・4班の5人の中で、今まで黙っていた塚田和博君に声をかけるのだった。
塚田君は、丸刈り頭だったが、5人の中ではただ一人、黒縁メガネをかけた、いかにも勉強ができそうな風貌の男子だった。身長は、津島君よりは高かったが、田中君たちよりは低かった。町田紘一先生が顧問をつとめる「読書倶楽部」のメンバーで、読書が好きな図書館男子だった。
「ハカセ(博士)」のあだ名は、津島君がつけたのだが、塚田君は、1年生の時、津島君と同じB組で、学業成績の順位(席次)がB組内で常に1位で、学年末に発表される学年席次も1位だったことによる。
それだけではない。これは津島君が「発見」したことなのであるが、塚田君の授業ノートは、非常によくまとまっており、字も丁寧で読みやすく、定期試験前の勉強にきわめて役に立つ「参考書」だったのだ。
そして、ここからが重要なのであるが、塚田君は、性格も温和で、誰に対してもやさしく公平にそのノートを貸したため、赤点(明和中学では定期試験で60点未満)を回避するための「虎の巻」として、定期試験前には、普段は授業中、居眠りをこいている1Bの運動部員たちの間で回し読み、回し写しされるのが恒例となっていたのだ。
すなわち、塚田君は、「クラスの頭脳」として一目置かれる存在だったのである。そして、このことは、2年生の新クラスである2Bにおいても、大運動会(5月中旬開催)後の興奮もさめやらぬまま、5月下旬に行われた1学期中間試験において、新クラスの運動部員たちに対しても、しっかり証明されたのである。
それは、担任の吉川先生に、
「このクラス、運動部員が多いわりには、中間の平均点が、やけにいいな・・・まさか、おまえら、集団でカンニングしたんじゃねーだろうな!カンニングしたら、ケツピン棒じゃすまねーからな!」
と言わせるほどの効果があったのだ。
しかし、そんな塚田君も、掃除さぼりの悪知恵となるとチト弱い。津島君が塚田君に「おまえはどうする?」と聞いたことに、田中君も手塚君も寺田君も、「なんでハカセに聞くんだよ?」と不満そうな顔をしている。
「えっ・・・ボ、ボクはいいよ・・・」
と、津島君からの「悪の誘惑」に、困ったような表情をして、どもるような口調で答える塚田君だった。
津島君は、それを聞くと、
「よし!ハカセは、4班のリーダーだからサボリなし!サボって楽させてもらうのは、オレたち4人だ!」
と、あっさり言うのだった。
塚田君は、それに対して何かをいいたそうな顔だったが、下を向いてしまう。その時、塚田君は思っていた。
「あのさ・・・この教室、たいして汚れてないんだし、換気もできたみたいだし、窓を閉めて、終わりにして、吉川先生に報告にいけば、それで終わりなんじゃないかな・・・なんで、わざわざサボる話し合いをする必要があるの?」
そうなのだ。その日の場合、誰がどうサボるかを話し合っている暇があったら、さっさと換気をおえて窓を閉めて、吉川先生に報告にいけば、めでたく特別教室の掃除終了なのであった。しかし、そんな余計なことは口に出さない、ある種の賢さが塚田君にはあり、それが、やんちゃ坊主が多いクラスの中にあって、おとなしいガリ勉タイプの塚田君が特段大きないじめを受けることもなく「生き延びて」いける理由の一つでもあったのだ。
「よぉ〜し!サボる順番は、じゃんけんで決めようぜ!」
と田中君。
「えっ!オレ、まだサボるって決めたわけじゃねーし!なあ、義之!」
と、あわてて、テニス部の手塚君が、話の流れを変えようとする。
話を振られたバレー部の寺田君も、あわてるように、
「あ、ああ・・・」
と返す。
「チェッ!おまえら、根性ねーなー!」
と田中君。
これでまた、誰がサボるのか、どうやってサボる順番を決めるのかで、4人の「会議」が10分以上繰り返される。これには、津島君から「リーダー」と指名を受けた塚田君も、呆れ顔だった。
結局、津島君の提案で、津島君と田中君が、月曜日から水曜日をサボり、そのサボっている間に、手塚君と寺田君がサボるかどうかを決めて、サボる決心がついたら、木曜日から土曜日の掃除をサボることに決まったのである。
「じゃあ、おまえら、あとは頼んだぞ!」
と、津島君と田中君が、第一美術室から出ていく。
すると、テニス部の手塚君が、
「この部屋さ、あんましっていうか、全然、よごれてねーし、窓閉めれば、それで、掃除おわりじゃねーか?」
と言い始める。もちろん、バレー部の寺田君もそれにうなづく。
ハカセこと「リーター」の塚田君は思うのだった。
「でしょ!だから、さっさと、窓閉めて、みんなで吉川先生のところに報告に行けば、その方がよかったんじゃないかって・・・」
「ハカセ?それで、いいだろ!?」
「おい、リーダー!!それでいいよな?」
寺田君と手塚君のその問いかけに、塚田君は、真っ赤な顔になりながらも、コクリと頷くのだった。
「はい!じゃあ、たりィー美術室掃除は、これでおしまい!」
「そうそう、おしまい!あ、リーダー、イエローカードには、リーダーが報告しといてくれよ!」
そう言って、寺田君も手塚君も、塚田君の返事を聞こうともせず、第一美術室を出て行ってしまうのだった。
第一美術室に一人残された塚田君。
「えっ・・・ボク一人で吉川先生のところへ行くの・・・やだなぁ・・・でも、ボク、4班のリーダーだもんな・・・」
塚田君は、不安になりながらも、津島君が自分のことを「リーダー」と決めてくれたことが、内心、うれしくてたまらなかった。
運動部員の掃除さぼりの片棒を担ぐこと、それは担任の吉川先生からケツピン棒でケツを叩かれても文句は言えない「悪いこと」「間違ったこと」だったかもしれない。しかし、塚田君は、運動部員の津島君たちの仲間に入れたような気持ちになりうれしかったのだ。
そして、吉川先生への掃除終了の報告を首尾よく成し遂げ、自分を「リーダー」と呼んでくれた津島君の期待にどうにか応えようと、勇気を振り絞り、担任の吉川先生が待つ体育館一階の体育館職員室へと、一人、トボトボと歩いていくのだった。
・・・・・・・・・・・・・・・・
通常、特別教室の掃除完了の報告は、その特別教室の管理責任者である教諭に行う場合が多いが、その日の第一美術室の掃除完了の報告は、担任の吉川先生にするように昼のSTで吉川先生自身から指示がでていたのだ。
「先生・・・第一美術室の掃除が終わりました・・・4班です・・・」
「おお、そうか・・・ご苦労・・・」
体育館職員室の吉川先生の机の脇に立って、塚田君が報告する。
ドキッ!ドキッ!ドキッ!
13年と数カ月の塚田君のこれまでの人生の中で、これほど心臓が高鳴ったことはなかったのではないか。
ドキッ!ドキッ!ドキッ!
吉川先生の机の上には、中1以来なじみのある黄色いケツピン棒が無造作におかれている。しかし、優等生の塚田君は、その棒でお尻を叩かれたことがまだ一度もなかった。昼のSTの教室で、また、体育の時間に、吉川先生が持つその黄色い棒を見るたびに、いつかは自分もその棒でお尻を叩かれるのではないかと想像し、心臓だけではない、ドキドキする心臓の鼓動にあわせるかのように、塚田君の白ブリーフの中の、まだまだ剥けきれない男性自身もドクン!ドクン!と脈を打っていたのである。
「この棒、教室で先生が持っているところをみるより、太くて、硬そうな棒だ・・・これでお尻叩かれたら・・・きっと、すごく痛くて・・・すごく恥ずかしい・・・」
ケツピン棒をみながら、そんなことを思っていると、ますます心臓がドキンドキンと高鳴ってしまう塚田君。そして、塚田君の心臓の高鳴りをどうにか抑えようとする理性に反抗するかのように、塚田君の学ランの下、スクールパンツである白ブリーフの中のイチモツも、心臓の鼓動にあわせるかのように、ドクン!ドクン!と脈打ち始めていたのである。
塚田君のその心臓の高鳴りが、吉川先生の耳にも届いたのか、何やら難しそうな「體育教育学」というタイトルの専門書に目をやっていた吉川先生が、急に顔をあげて、塚田君のことをみるのだった。
「4班って、誰がいたっけ?」
「え、えーと・・・津島君、田中君、手塚君、寺田君、そ、それと、ボ、ボクです・・・ご、5人です・・・」
塚田君は、自分の声がうわずっていることに気がつき、マズイと思っていた。
「5人で掃除したんだろうな?」
「えっ・・・は、はい・・・も、もちろん・・・です・・・」
吉川先生が、再び、睨むように、塚田君のことをジロリと見上げる。塚田君は、「あっ、まずい・・・絶対、バレてる・・・」と思った。一方、吉川先生は、「コイツ・・・絶対、オレにウソついてんな・・・」と思っていた。
吉川先生は、しばしの無言。さっきの専門書に再び目を落としている。
ドキッ!ドキッ!ドキッ!ドキッ!ドキッ!ドキッ!ドキッ!ドキッ!ドキッ!
その間は、塚田君にとって、永遠に続かのように長く感じられた。手のひらが汗ばんできていた。
「ぜったいに、おこられる・・・どうしよう・・・まずいよ・・・その棒で、お尻、叩かれちゃうよ・・・」
塚田君は、吉川先生の脇に立って、もう顔はゆでだこのように真っ赤だった。もう、手のひらだけではなかった。塚田君の額からは、汗がにじみでてきている。塚田君は、右手人差し指で、自分の鼻からずり落ちそうな黒縁メガネを何度も上げるのだった。
さらに悩ましいことに、塚田君の股間のイチモツが、心臓の高鳴り以上に、
ドクン!ドクン!ドクン!ドクン!ドクン!ドクン!
と、熱く、そして、ズシン!ズシン!と重くむず痒く脈打ち始めてしまったのである。
吉川先生の沈黙・・・それは、塚田君の心の中に、「あのケツピン棒で初めてお仕置きされるのでは・・・」という、不安、緊張、焦燥感を生むのに十分なくらいのインパクトがあった。
そして、塚田君の心の中に惹起された、その精神的緊張の高まりは、塚田君の股間を強烈に刺激していたのである。第二次性徴を迎えているとはいえ、まだまだ男としては未熟な塚田君には、自分の身体の中で起こるその性的な高まりをコントロールすることは到底できなかった・・・。
「せ、せんせい・・・は、早く、な、何かいってください・・・ボ、ボク、そ、その棒で、お、お尻を叩かれるんですか・・・」
しかし、塚田君のその願いもむなしく、塚田君の前に座る吉川先生は、まるで塚田君をじらすかのように無言のままだった。
ドキッ!ドキッ!ドキッ!ドキッ!ドキッ!ドキッ!
ドクン!ドクン!ドクン!ドクン!ドクン!ドクン!
そして、哀しいかな、吉川先生の言葉を待つまでもなく、塚田君は、白ブリーフに包まれた己のイチモツの芯を、急にツゥ〜ンと引っ張られるような妙な感覚に襲われるのだった。それと同時に、熱くて重くてむず痒い、なんとも言えない気持ちのよさが、塚田君の股間から脳天へと突き抜けていく・・・もう我慢することなどできなかった・・・。
ドクン!ドピュ!ドピュ!ドピュ!
ドクン!ドピュ!ドピュ!ドピュ!
ドクン!ドピュ!ドピュ!ドピュ!
まだ剥けきれていない塚田君の男性自身が、塚田君の意思に反して、白ブリ―フの中で、何度も脈打ち、その先端からクリーム色の粘液がドピュ、ドピュと噴出される。塚田君がはく白ブリーフの中に生温かいムニュ〜とした粘液が満たされていく・・・。
「あっ・・・あぁ・・・・」
塚田君はなんともいえない切ない声を上げて、あわてて、学ランの股間を両手で押さえて、その場にしゃがみこんでしまうのだった。
「つ、塚田・・・ど、どうしたんだ?腹でも痛いのか?」
吉川先生は、驚いたように専門書から目を離し、自分の座っている横でしゃがみこんでいる塚田君の後ろ姿を見下ろすのだった。
「は、はい・・・ちょ、ちょっと・・・きゅ、急におなかが・・・」
そんな塚田君の様子をみて、吉川先生は、「しょーがーねーなぁー」といった顔つきをする。
そして、
「よし、今日は帰っていいぞ!腹が痛いんだったら、早く便所に行け!」
と言うのだった。
塚田君は、吉川先生に背を向けたまま、そして、腰を思いきりひいて、吉川先生の方へケツを突き出したへっぴり腰の恰好で、
「は、はい・・・あ、ありがとうございます・・・し、失礼します・・・・」
と言って、体育館職員室の扉の方へ向うのだった。それがお腹を痛そうにする演技だと思っていたのだ。
吉川先生は、塚田君が、自分の方に向くこともなく、自分の方へケツを突き出したまま、ソロソロと歩き去っていく、その恰好をみて、思わず吹き出しそうになる。
そして、
「アイツ、本当に、腹が痛いのかよ・・・まじめそうな顔しやがって・・・そのうち、アイツのケツにもこの棒で指導する時が来るかもしれんな・・・」
と思ってニヤリとするのだった。
塚田君が体育教官室の扉を開けようとしたまさにその時、吉川先生がうしろから、
「おい!塚田!」
と、塚田君を呼び止める。
ドキッとしてへっぴり腰のまま振り返る塚田君。その額には汗がにじみでていて、顔全体が真っ赤だった・・・。
「は、はい・・・」
「明日は、お前が報告にきたら、俺が一緒に美術室にいって点検するから、それまで4班全員、美術室で待機しているようにって、アイツらに伝えといてくれ!いいな!」
「は、はい・・・わ、わかりました・・・」
「よし!行っていいぞ!」
とだけ言うと、吉川先生は、再び、いままで読んでいた専門書に目を落とすのだった。
「は、はい・・・し、失礼します・・・」
そう挨拶すると、塚田君は、学ランズボンの腰は引けたまま、へっぴり腰の恰好で、なんとも気持ち悪そうな表情を顔に浮かべながら、体育館職員室をでていくのだった。
体育館(屋内運動場)へと続く廊下に誰もいないことがわかると、塚田君は、あわてるように、体育館一階にある便所の大便個室へとかけこむのだった。
カチャ、カチャ、カチャ・・・・
大便個室の中で、立ったまま、塚田君はズボンのベルトを緩め、ズボンを膝まで下ろす。ツ〜ンと青臭い栗の花の臭いが塚田君の鼻を憑く。恐る恐る、下をみる塚田君・・・スクールパンツである白ブリーフの「2B 塚田」と黒マジックで描かれたフロント部分に、ドロッとしたクリーム色の粘液がベッタリと染み出てきていた。このままでは、もう少しで、学ランまでシミになってしまうところだ。
「あぁ・・・また汚しちゃった・・・これじゃ、かあさん、気がつくよな・・・」
塚田君は、自分の身体の変化が母親に気づかれてしまう恥ずかしさに顔を紅潮させるのだった。
まだ、トイレットロールが普及していない時代だった。その大便個室の壁には、
「尻を拭く時は、一用便につき、一人三枚まで」
との張り紙がしてあった。
まじめな塚田君は、その張り紙の指示通り、ゴワゴワと硬い、灰色をしたトイレ備え付けのちり紙を3枚とる。
まずは、一枚目と二枚目のちり紙で、スクールパンツの中と外を汚したクリーム色の粘液を丁寧にきれいにふき取るのだった。塚田君は、そのゴワゴワとしたちり紙で、己のイチモツをふき取る感触が、好きになれなかった。
次に3枚目のちり紙。
塚田君は、それを約3対7の割合で丁寧に折って、3の部分を白ブリーフの腰ゴムの内側に入れ、7の部分の外側に垂らし、己の精液で汚れた「2B 塚田」と描かれた部分を丁寧に覆って、白ブリーフについた汚れが学ランにつかないようにする。そして、そのちり紙がズレないように、そぉっと学ランズボンを上げて、再び、
カチャ、カチャ、カチャ・・・・
とベルトを締めなおすのだった。もちろん、一枚目と二枚目のちり紙は、まだ水洗化されていない、ポットン・トイレの便器の下にある「便槽」の奈落へポイと捨てるのであった。
ズボンを上げた塚田君は、
「あぁ・・・リーダーってつらいよな・・・」
とつぶやきながら、トイレの大便個室を出ていくのだった。
4 石井君の伝令
翌日、火曜日の放課後。
「やべっぇ・・・練習、まにあわねぇ・・・町田のオッサン、頼むから、6限のあとだけはオレに説教しないでくれ・・・また先輩に正座させられちまうよ・・・」
6時間目の授業終了後、明和学園・中等部2年B組の津島裕二君が、「明和中」の文字が刺繍されたサッカー部のユニフォームもほこらしげに、中学校舎の階段を一目散に駆け降りていく。校舎は戦災を奇跡的に逃れた木造校舎だ。津島君が階段を降りるごとにギシギシ、ミシミシと音がする。
2年生に進級しても、津島君のやんちゃぶりは相変わらず。
その日の2年B組の6時間目は、2年A組担任で、現代国語担当の町田紘一先生(52歳)の授業だった。その授業で、しっかり居眠りを決め込んでいた津島君は、授業終了後、町田先生からみっちりお説教を食らってしまい、放課後のサッカー部の練習開始に遅刻ギリギリだったのだ。
「コラァ!津島!危ないぞ!階段では走るなって何度いったらわかるんだ!」
途中、2年C組担任で、数学担当の生方久男(うぶかた ひさお)先生(25歳)に注意されるも、津島君は、
「ィ〜〜ス!!」
とだけ返事をし、さらにスピードを上げ、2段飛びで階段を駆け降りていく。
果たして、中学校舎から校庭に飛び出してきた津島君に、今度は、校庭のど真ん中あたりから声がかかる。
「おーい!裕二!」
その野太く、よく通る声は、津島君の中1以来のクラスメート、2年B組の石井健介(いしい けんすけ)君だった。石井君の部活は野球部。用具出しなど、練習の準備をする中1の後輩たちの指導を校庭でしていたのだった。
津島君は、石井君のその声を聞き、ちょっとイラついたような顔つきをしつつも、立ち止まって石井君の方を向くと、
「あと!あとで!」
と返答をする。津島君は、背は小さいものの、石井君に負けず劣らずのよく通るデカい声を出すのだった。
そんな津島君をみて、石井君は、さらにデカい声で、
「裕二!聞け!ハカセが!せっきょー終わったら!第一美術室に!ぜってー!来い!だって!今日は!かばえねー!だって!」
というのだった。
それを聞いて、津島君は、ハッと何かを思い出したような顔つきをする。そして、くるりと向きをかえると、「第一美術室」のある「芸術科校舎」の方へと走っていくのだった。
・・・・・・・・・・・・・・・
「裕二、まだこねぇーのかよ・・・おっせーな・・・ハカセ、アイツにもきちんと伝えたんだよな?今日のイエローカードの掃除点検のこと。」
火曜日の放課後。第一美術室で、2Bで野球部員の田中義人君が、ハカセこと塚田和博君にそう聞くのだった。
「あのとき、津島君いなかったから・・・だから、石井君に伝言、頼んどいたけど・・・」と答える、塚田君。
「えっ!健介にかよ!?大丈夫かなぁ、アイツさあ、野球部でもよく伝令忘れたり、間違ったりして、ケツバットされてんだよな・・・」と、田中君。
田中君のその言葉を聞いて、塚田君の表情が曇るのだった。
塚田君の心配そうな表情をみて、バレー部の寺田義之君が、
「おい、リーダー!!しっかりして下さいよ!」
と、塚田君の学ランの背中をバチン!と叩くのだった。
「い、いたい・・・ゴホッ・・・ゴホ、ゴホ・・・」
寺田君に背中を思い切り叩かれて、塚田君は咳き込んでしまう。そんな「リーダー」塚田君の責任を追及するかのように、寺田君は続ける。
「あーあ、このまま津島がこないと、俺たち全員、ケツピンなんじゃねーか?どうするんだよ!リーダー!!」
寺田君のその意地の悪い言い方に、塚田君は、困って泣きそうな表情をするのだった。
そんな自分たちの「リーダー」の表情と姿を面白そうにニヤニヤ顔で見ながらも、テニス部の手塚君は、興味津々で、野球部の田中君に聞く。
「なあ、田中、やっぱり、うちの野球部でも、ケツバットあるのか?」
「ああ、野球部だからな。3Aの杉本さんって知ってる?」
「ああ、あの先輩、オレと同じ駅でさあ、朝とかよくみかけるよ・・・」
「あの人、ケツバット好きでさあ、しかも手加減、一切なし。ケツにガツーンって響いて、まじめに泣くぜ・・・」
「こえぇー、でも、ケツバットやられてるから、野球部のヤツらは、ケツピンなんて平気だろ?いいよな・・・」
「ま、まあな・・・イエローカードのケツピンなんて、こわくねーけど・・・」
田中君はそう答えるも、手塚君が話しかけてくることに少しうるさそうな表情をみせ、話題を変えるかのように、
「そんなことよりさ・・・さっきから思ってたんだけどさ・・・あの彫刻、すげー、卑猥(ひわい)じゃねぇか?」
と、ニヤニヤしながら、第一美術室の黒板の前に置かれた白い「彫刻」を指さすのだった。
5 ダビデのチンコは・・・
その日の第一美術室には、前日の月曜日にはなかった白い彫刻が1体、黒板の前、教壇の上におかれたちゃぶ台ほどの高さのある木製の台の上に置かれていた。その像は、デッサン授業用の石膏製・男性彫刻で、高さは120cmほどだった。かなりの重さがあるようで、中学生男子が数人かかっても、そう簡単には動かせないように見えた。
「なあ、コイツのチンチン、ホーケーじゃねぇか?」
と、田中君が、その男性彫刻を指さしていうのだった。
「あ、本当だ!」
「おもしれー。」
と、手塚君と寺田君。
田中君、手塚君、寺田君の3人は、ニヤニヤしながら、その白い男性彫刻に近づき、股間を興味津々に眺めるのだった。
2B担任の吉川進先生の保健体育の授業での「英才教育」のお陰で、その時すでに、明和学園・中2の生徒たちの辞書には「包茎」という単語が加わっていた。

その男性彫刻は、ミケランジェロ作「ダビデ像」の学校教育用・石膏レプリカであった。

そんな三人とは少し距離をおいて、塚田君は、中1・3学期の「じっちゃん」こと村田兼良(むらた かねよし)先生(美術史担当)の授業を思い出していた。
美術の村田先生は、その時なんと92歳のおじいちゃん先生。公立校と違い、私立校である明和学園には、当時、はっきりとした定年がなかったため村田先生のような90代のおじいちゃんでも、健康で頭脳明晰でさえあれば、まだまだ現役教諭でいられたのである。
村田兼良先生は、慶応3年生まれ。江戸幕府の御用・表絵師・村田兼信の末子で、徳川慶喜のことを「上さま」と呼んでは、明和学園の生徒たちを笑わせていた。
そんな村田先生も、健康とはいえ、寄る年波には勝てず、板書するとき手が震えるようになってから、授業中、黒板には一切何も書かなくなった。いつも教卓の後ろの椅子に座って、ボソボソと小さな声で、お話をするだけ。そのため、ほとんどの生徒は、村田先生の授業中、深い眠りに落ちていたのである。
それでも、村田先生は、定期試験に出題される部分になると、必ずと言っていいほど、教室の生徒を笑わせようとしていたのだ。もちろん、そのことにいち早く気がついていた生徒もいた。ハカセこと、塚田和博君もその一人である。
村田先生が、ミケランジェロのダビデ像の「おちんちん」について触れた時もそうだった。
「君たちは笑うかもしれんがね・・・当時、すなわち、この像が完成したルネサンス期にはだね・・・割礼しない、ちょっと小ぶりの、おちんちんがだね・・・美しいとされていたんだな・・・フォ、フォ、フォ・・・」
シーンと静まり返った教室。塚田君がノートをとる鉛筆の音だけが響いている。塚田君は、思わずニンマリする。
「あっ、村田先生の『フォ、フォ、フォ』が出た!ここは試験に出るかもしれないぞ!」
塚田君は、あとで忘れないように、その部分に、朱色鉛筆で、二重丸をつけるのだった。その時の塚田君には、「割礼」の意味がわからなかった。しかし、図書館男子の塚田君である。その日の放課後、すぐに学校の図書館へ行き、「割礼」の意味を調べたのである。
その時の教室の静けさに不満だったのは、もちろん、村田先生だ。生徒たちを「睡眠術」にかけ、塚田君以外の生徒を、深い眠りに落としているという自覚が、村田先生にはなかった。
「戦争前は、ここでみな、大笑いしたもんじゃがな・・・近時の子らは、どうも張り合いがなくて、つまらんのぉ・・・ダビデ像は期末試問で出題しようと思っているんじゃがな・・・大丈夫じゃろか・・・」
村田先生の期末試験は、「超大甘」、奈良の大仏級の「仏」の試験だった。三択問題が、全部で20問出題され、配点は、1問10点。そう、100点満点とすべきところ、200点の配点をして、あらかじめ、「ゲタ」をはかせていたのである。
果たして、3学期の「美術」の期末試験(「美術史」の知識を問うペーパー試験)には、問3番で、次のような問題が出たのである。
三 ミケランジェロ作ダビデ像,其ノ割礼セラレザリシ理由ヲ問フ.
甲) 政治的理由ニ依ル
乙) 宗教的理由ニ依ル
丙) 美的理由ニ依ル
もちろん、上の問題の正解は(丙)だ。村田先生の授業をしっかりと聴きノートにとっていた塚田君、そして、塚田君のノートを写させてもらった津島君は、大正解であったことは述べるまでもない。そんなことを思い出しながら、思わずニヤニヤしてしまう塚田君だった。
(太朗注:ミケランジェロのダビデ像が、割礼されていない理由には、諸説あります。)
6 野球部・チンチン検査
「おい!リーダー!なにニヤニヤしてんだよ!」
と、自分たちの後ろで塚田君がニヤニヤしながら自分たちのことをみていることに気がついたバレー部の寺田君が、塚田君の方へ近づいてくるのだった。
「そうだよ!おまえ、なにニヤニヤしてんだよ・・・きもちわりぃーな・・・」
寺田君だけでなく、田中君と手塚君もそう言いながら、塚田君の方へ近づいてくる。
黒縁メガネをかけた塚田君のニヤケ顔から笑みがスゥと消える。自分のニヤニヤ顔を3人に見られてしまった塚田君は、ハッと我に返り、
「ま、まずい・・・」
と思う。
「な、何か言わないと・・・」
塚田君は、自分がニヤニヤしていたことの言い訳を必死で探していた。しかし、寺田君、田中君と手塚君の3人は、遠慮なく、塚田君の方へ迫ってくる。
今度は、テニス部の手塚君が、ニヤニヤしながら、意地悪く、
「ハカセのチンチン、ホーケーなのか気になるよなぁ。」
と言うのだった。
それを聞いた寺田君と田中君も、意地悪くニヤニヤしながら、
「そうだぜ・・・気になるよな。」
「よし!俺たちが検査してやる!」
と言う。
「えっ・・・・」
と、思わず声を出す塚田君。自分に迫ってくる3人によって、塚田君は、あっという間に、第一美術室の後ろの壁に押しやられてしまうのだった。
野球部の田中君が、バレー部の寺田君とテニス部の手塚君に、「よし!やっちゃえ!」とばかりに目配せする。
「よし!」
「よし!」
田中君の指示に、待ってましたばかりに、寺田君と手塚君は、塚田君の後ろへと素早く回ると、塚田君の両手を後ろへまわして押さえつけてしまうのだった。
「は、はなして・・・や、やめてよ・・・」
塚田君は、蚊の鳴くような声を出して、懇願する。そして、自分の両手を後ろからつかんで押さえこんでいる寺田君と手塚君からどうにか逃れようと抵抗するのだった。しかし、運動部員2人の力を、読書倶楽部の塚田君は跳ねのけることができなかった。
「フフフ・・・ハカセのチンチン、いままでしっかりみたことなかったよな・・・今日は、俺たちが、おまえのチンチンをしっかり検査してやるぜ!」
そういうと、野球部の田中君は、カチャカチャカチャと塚田君の学ランズボンのベルトを緩め、ホックを外そうとするのだった。
「や、やめて・・・ほ、ほんとに、やめて・・・」
塚田君は、いまにも泣き出しそうな真っ赤な顔をして、絞り出すような小声でそう懇願する。しかし、野球部の田中君は、塚田君のそんな懇願を無視するかのように、顔にサディスティックな笑みを浮かべながら、ホックを外して、塚田君の学ランズボンの「社会の窓」のジッパを一気におろすのだった。
・・・・・・・・・
「チンチン検査」。それは、田中君が、中1の時、野球部の夏合宿で、中3と高1の先輩から押さえつけられて受けた恥辱の検査だった。
明和学園野球部では、夏合宿中、新入りの中1部員が1晩に1人、就寝中に、先輩たちから押さえつけられて、チンチンの皮を情け容赦なくひん剥かれる「チンチン検査」と呼ばれる伝統の儀式があった。
もとより、野球部・夏合宿に初参加の中1部員たち。合宿中は、中1専用の練習とトレーニングメニューが用意されているとはいえ、ほぼ全員が昼間の練習とトレーニングの疲労のため、夜は爆睡状態。そこを突然、先輩たちから襲われるわけだから、中1部員のほぼ全員が、抵抗することもできず、ジャージとパンツを一気にガバとズリ下ろされて、あっという間に、御開チ〜ン状態になってしまうのだ。中には、目を覚ますことなく、寝たまま、「チンチン検査」を受ける中1部員もいるらしい。
「コイツのチンチン、むけるかどうか、検査するんだ!しんせーほーけーだったら、手術だからな!おい、山本!おまえ、やれ!」
まるで医者のような口ぶりで高1の先輩が、お供の一人である中3部員の山本君に命令する。
中1部員たちが寝る大部屋に「押し入って」来た野球部・高1と中3の先輩たちに押さえつけられ、ガバっと白の体育用トレーニング短パンとパンツを下ろされて、すでに御開チ〜ン状態の田中君。ハッと目が覚めた時は、すでに遅し、自分の下半身が、スゥ〜と妙に涼しかった。すごく怖くて、動くことができない田中君。ジッと両目をつむって、先輩たちから受ける「チンチン検査」を待つしかなかった。
先輩の命令には絶対服従の野球部だ。高1の先輩のその命令に、中3部員の山本君は、
「ィ〜ス!」
と短く返事をすると、田名君の丸出しになったまだまだ剥けきれないホーケーチンコを、右手の親指と人差し指でムンズとつまみあげ、その皮を遠慮会釈なく一気に剥き上げようとするのだった。
「いっ、いてぇ・・・」
思わず悲鳴を上げてしまう田中君。田中君のホーケーチンコの亀頭の先端は、包皮の割れ目からその真っ赤な鈴口をほんのちょっとのぞかせていたが、包皮から亀の頭を出すことはできないでいた。
それをみて、田中君を囲む先輩たちの目が、サディスティックにギラギラと輝きを増す。もちろん、田中君のその悲鳴は無視され、
「まだまだ、もう一丁!山本、もっとしっかりむきあげろ!」
と、高1の先輩は命令する。
「ィ〜ス!」
と、中3の山本君は再び短く返事をすると、ニヤニヤしながら、田中君のホーケーチンコをさっきよりは少し強めにグイっと剥き上げようとする。
「いてぇ・・・」
再び、田中君の切ない悲鳴。しかし、次の瞬間、
「あっ!」
と、先輩たちの声が上がる。
田中君のホーケーチンコの包皮がベロンと裏に返えるように剥きあがり、白い恥垢に覆われた赤い亀頭がヌッと丸出しになったのだ! 田中君は、股間だけでなく、己の男性自身の先っぽに、スゥ〜とヒンヤリとした冷気を感じるのだった。
「うわぁ!チンカスだ!きったねー!!」
そういって、つまんでいた田中君のチンコを投げ出すように手放し、思わず右手をひっこめる中3の先輩・山本君。そんな後輩に、高1の先輩は、
「山本!何やってんだ!田中のチンコをシコれ!」
と命令を飛ばす。
その命令に、山本君は、一瞬、戸惑ったような顔をするも、すぐに決心したような顔つきになると、
「ィ〜ス!」
と短く返事をし、今度は、田中君の剥き上げられ亀頭が顔を出したチンコをムンズとつかみ、それを根元から筒先まで、上下に、しっかりと、扱き始めるのだった。
「い、いたい・・・」
まだまだ剥き上げられたばかりの田中君のホーケーチンコの亀頭は、包皮の摩擦による刺激に敏感だった。
シコ!シコ!シコ!シコ!シコ!シコ!
「い、いたい・・・」
しかし、痛いのも最初のうちだけ。中3の先輩・山本君にみっちりと休みなく竿を扱き上げられ、田中君のチンコはすぐさま元気に充血してきて、その股間は、熱くて重い痒さと抗しきれないほどの快感につつまれていく。
シコ!シコ!シコ!シコ!シコ!シコ!
「あっ・・・あぁ・・・」
ドクン!ドクン!ドピュ!ドピュ!ドピュ!
ドクン!ドクン!ドピュ!ドピュ!ドピュ!
田中君は、ほどなく、なんとも切ないよがり声を上げて、中3の先輩の右手のひらの中で、男の青春の迸りを爆発させてしまうのだった・・・。
「あー、コイツ、もらしやがって・・・きったねーなー・・・男だったら、こんくらいガマンしろ!!」
そう言うと、中3の先輩・山本君は、ネチョーとした粘液がこびりついた右手で、田中君の五厘刈りの青白いジョリジョリ頭を撫でまわし、
「あーばっちぃ!!」
と言って、最後にバコ〜ン!と一発、田中君の頭を叩くのだった。
高1の先輩は、その光景をサディスティックな目で見下ろしながら、
「田中!我慢できなかった罰だ!!明日、中学朝練の前にケツバット10発!!山本!!田中のこと、しっかり教育しとけよ!!」
と言うと、中1の大部屋から出ていくのだった。
田中君のチンコを扱いた中3の山本君は、高校生の先輩のその命令を聞いて、
「ィ〜ス!」
とうれしそうに返事をして、ガッツポーズをとると、茫然自失といった表情の田中君を睨みつけ、
「先輩からの命令だ!田中、明日、朝練前、おまえは、中学部員全員の前で、パンツ一丁でケツバット10だ!いいな!覚悟しとけ!」
と言うと、田中君の返事を待つこともなく、高1の先輩の後を追うように、中1部員たちの寝る大部屋を出ていくのだった。
ベチィ〜ン!!
「うぅ・・・シタ!!」
ベチィ〜ン!!
「うぅ・・・シタ!!」
ベチィ〜ン!!
「うぅ・・・シタ!!」
果たして、翌朝、中学朝練の前の整列で、一人パンツ一丁、前に出された田中君のブリーフ一丁のケツに、山本先輩のノック用の木製バットがさく裂していた。
中3、中2、中1と3列横隊の野球部員たちの方を向いて、田中君は、パンツ一丁、万歳するように両手をスクと上げ、上体をやや傾けて、白ブリーフ一丁のケツを後ろに突き出している。そのケツめがけて、中3の山本先輩が握るバットが、情け容赦なく炸裂する。
1発毎に苦し気な表情を浮かべる田中君をみながら、中3・中2部員たちは、ニヤニヤと、サディスティックな笑いを浮かべている。そして、田中君と同期の中1部員たちは、田中君に同情しつつも、今夜の「チンチン検査」の標的は自分なのではないかと、気が気ではない。
ベチィ〜ン!!
「うぅ・・・」
約束のケツバット10。10発目の打撃が、田中君の白ブリーフのケツに容赦なく炸裂すると、田中君はうめき声をあげながら、ケツを両手で庇うようにして、その場にしゃがみこんでしまう。
「よし!田中!さっさと宿舎に戻って、ユニに着替えてこい!!5分以内に戻って来れなかったら、ケツバット10発追加だからな!!さあ、立っていけ!」
山本先輩は、そう田中君に命令すると、田中君の白ブリーフのケツを、穿いていた黒のトレーニングシューズで、バチィ〜ン!!と蹴り上げるのだった。
先輩にケツを蹴り上げられ、思わず悲鳴を上げそうになる田中君。しかし、田中君は、グッとこらえて、何事もなかったように、
「ィ〜ス!」
と返事をすると、悔しくて泣きたくなる気持ちをグッと抑えて、ダッシュで宿舎の1年生の大部屋へと戻って行くのだった・・・。
・・・・・・・・・
そんな中1の夏合宿で、先輩からされた「チンチン検査」の仕返しをするかのように、ギラギラした目をして、田中君は、クラスメートの塚田君の学ランズボンの腰に両手をかけていた。
田中君だけでなかった。バレー部の寺田君も、テニス部の手塚君も、中1の夏合宿では、先輩たちから、似たような「性的なイジリ」を受けていたのである。中高6年一貫の男子校の運動部の合宿、特に、中1が初めて参加する夏合宿では、先輩からのそういった性的いたずらが、通過儀礼として大なり小なり存在したものなのである。
もう抵抗はできないとあきらめた塚田君は、「あーー、みんなに見られちゃう・・・恥ずかしいよ・・・」と思って、両目をギュとつむる。塚田君の顔はもう耳まで真っ赤だった。
「田中、早くおろしちゃえよ!!」
と、寺田君が、田中君をけしかける。
「ああ、もちろん!でも、まず、ズボンからだな!!」
ニヤニヤ顔の田中君は、そう言うと、塚田君の学ランズボンを、ガバっと膝のあたりまで、一気におろしてしまうのだった。
「うわぁ!!きったねー!!」
思わずそう言ってしまったのは、手塚君だった。そう、清潔好きの手塚君が目にしたものは、塚田君の、茶色いゴワゴワの染みがフロント部分にべっとりとついたスクールパンツ、すなわち、白ブリーフだったのだ。
塚田君は、前日、体育館職員室の吉川先生の横で、パンツの中に射精してこしらえてしまったその染みを、母親にバレるのが恥ずかしくて、そのパンツを一晩はきっぱなしにしてしまったのであった。
そう、その時の塚田君にとって、自分のホーケーチンコを見られることよりも、パンツの染みをクラスメートに見られることの方が恥ずかしかったのである。吉川先生の横に立ち、ケツピン棒でお尻を叩かれることを考えていたら、急に、おチンチンが硬く、熱く、むず痒くなってきて、ドピュドピュと精液をパンツの中に漏らしてしまったことが、田中君たちにバレてしまうと思ったのだった。
しかし、それは塚田君の杞憂であった。
「うわぁ!おまえ、きのう、夢精したのか!」
「うわぁ!すごいシミ・・・もう中2なんだから、シコれよ!!」
と、田中君と寺田君は、ニヤニヤしながらも、塚田君に同情する表情を浮かべるのだった。
と、その時だった!!
「おい!!おまえら、そこで何してるんだ!!」
と、美術室の入口のドアの方から、デカい声が聞こえてくる。
塚田君の染みつきブリーフをガン見していた田中君、寺田君、手塚君の3人だけなく、今にも泣きそうな真っ赤な顔の塚田君も、ギョッとして、その声が聞こえてきた方を向くのだった。
7 サッカー部・チンチン検査
田中君、寺田君、手塚君、塚田君の4人が、第1美術室の一番後ろで、なにやら寄り集まってやっている。しかも、塚田君は、学ランのズボンを下までおろして、染み付きパンツが丸見えだ!
石井君の伝令を受けて、美術室に急いでやってきた津島君は、その光景を目にして、驚いたように、
「おい!!おまえら、そこで何してるんだ!!」
と、デカくてよく通る声を上げるのだった。
田中君、寺田君、手塚君、塚田君の4人が、ギョッとして、津島君の方を見る。
「なーんだ・・・裕二かよ・・・」
「そうだよ!てっきり、イエローカードかと思っただろ!」
「ったく、こんな時に、イエロ―カードのマネなんてすんなよ・・・」
「えっ・・・オレ、マネしたわけじゃねーけど・・・そんなにそっくりだったか?」
「ああ、そっくり、おまえ、イエローカードみたいな体育教師になるといいかもな!」
「えっ・・・ふざけんなよ・・・オレが、学校のセンコーに・・・・そんなのあるわけねーよ・・・」
クラスメートの指摘に言い返しながらも、まんざらでもない表情を浮かべる津島君。
「ねぇ・・・もうズボン上げていいでしょう?」
そんな中、塚田君がいまにも泣きそうな声を上げるのだった。
「ハカセ、どうしたんだ?なんでズボン下げてんだよ?!」
と言って、津島君は不思議そうな表情で塚田君の姿を見る。もちろん、津島君の視線は、塚田君の泣きそうな顔から、だんだんと下の方へと行き、塚田君の茶色いゴワゴワの染みのついたスクールパンツのところで、ピタリと止まる。
「も、もう・・・そんなにジロジロみないで・・・ボクのパンツ・・・」
塚田君は、津島君にも自分の染み付きパンツを見られてしまったことを悟り、恥ずかしくて、再び顔が真っ赤になるのだった。
津島君は、ニヤケそうになる自分の顔を必死で引き締めながら、
「ハカセ、ズボン早く上げろよ!それから、パンツ、たまには洗濯しろ!!」
と、また教師のようなことを言うのだった。
「ほらな!いまのセリフ、イエローカードそっくり!!」
と、田中君が、早速ツッコミを入れる。寺田君と手塚君は大笑いだった。
一方、自分が「1週間パンツはきッパ星人」だと津島君に誤解されたと思った塚田君は、真っ赤な顔のまま、下を向いてしまうのだった・・・。
しかし、寺田君は、少し不満げな表情で、
「チェッ・・・ハカセのチンチン検査、もう終わりなのかよ・・・つまんねーの!」
と言う。
「チンチン検査?」
と津島君が驚いたような表情を見せる。
「だってさー、コイツ、俺たちのリーダーのクセに、あの彫刻のホーケーチンコみて、ニヤニヤしてんだぜ!」
と、手塚君。

「そうそう、だからさ、オレたちで、ハカセのチンコ、検査しようってことになって・・・」
と、田中君。
津島君は、月曜日にはなかったデッサン授業用のダビデ像の石膏レプリカをみてニヤリとするも、すぐにまじめな顔になって、
「ハカセ!!おまえ、ホーケーか?」
と聞くのだった。
塚田君は、津島君のやけにまじめなその問いかけに、さっきからの真っ赤な顔のまま、「う、うん・・・」と言って、コクリと頷くのだった。津島君のその時の問いかけ方には、ウソをついたり、答えなかったりしたら、絶交だぞ!とでも言っているかのような迫力があった。
「よし!聞いたか?ハカセはホーケーだって!もうわかったからいいだろ!!チンチン検査はなしだ!」
津島君は、田中君、寺田君、手塚君のことを睨みつけながら、再び教師のように、きっぱり言うのだった。
しかし、寺田君は、まだ少し不満らしく、
「チェッ!」
と舌打ちしてしまう。
それを聞いて、津島君は、寺田君のことをギロリとにらみ、
「おまえだって、ホーケーだろ?」
と言うのだった。
「うっせーな・・・そんなことどうだっていいだろ・・・だったら、裕二はどうなんだよ?」
と、寺田君が色をなして聞き返えしてくる。
「ああ、ホーケーだよ!悪いか、それが!」
と、津島君は、堂々と答えるのだった。そして、さらに、
「田中だって、手塚だって、ホーケーだろ!!海パンに着替える時、オレ、みたんだからな!!」
と、田中君と手塚君の方をにらみつけて言うのだった。
「ま、まあな・・・」
「ま、そうだけどさ・・・」
と、田中君と手塚君。
その場に流れる気まずい沈黙。
しかし、田中君がその場の気まずい空気を変えるかのように、急にニヤニヤして、
「でもさ・・・サッカー部でもチンチン検査あるんだろ!?裕二、この前、言ってたじゃん、夏合宿でチンチン検査あったってさ!」
と、津島君に言うのだった。
その時、津島君は、ちょっとだけ反省していた。「2Bの頭脳」であるハカセこと塚田君を庇うために、まじめになり過ぎたことを。そして、田中君が、「チンチン検査」の話に水を向けてくれたことに、素直に乗ったである。
「ああ、もちろん!!サッカー部のチンチン検査はだな!!こうやって・・・・」
そういうと、津島君は、美術室の教壇に上り、黒板の前のちゃぶ台ほどの高さのある木製の台の上に置かれたダビデ像の後ろにまわると、腰をグッと落として、両脚でダビデ像の腰のあたりを挟み込むようにするのだった。ダビデ像は、120cmほどしかなかったが、2Bでは一番背が低い津島君が腰をグッと落とすと、両膝がダビデ像の腰の当たりにちょうどくるのであった。グッと腰を落とした津島君は、「空気椅子」に座った状態だが、腰をグイと後ろに引き、ケツをプリッと少し上げて、黒板の「粉受」(黒板のチョークや黒板消しを置く部分)のやや下の壁の部分に白短パンのケツをペタっとつけて体勢を安定させるのだった。

寺田君と手塚君は、いったいこれから何が始まるのかと、興味津々の表情で、それを眺めている。一方、以前、サッカー部の「チンチン検査」について聞いたことがある野球部の田中君は、ニヤニヤしながら、津島君のエロ話が始まることを期待した表情で眺めている。そして、ハカセこと塚田君は、再び耳まで真っ赤になり、ドギマギした表情で、津島君のことを見つめている。
「サッカー部のチンチン検査はだな・・・こうやって、高2の先輩が、サカパン下ろしてフリチンになったオレたち中1部員の後ろに一人一人ついてだな・・・俺たちのチンコをこうやってつかんでだな・・・『なんだ、おまえ、まだホーケーなのか、今のうちしっかり剥き上げとかねぇと、いざというとき、女の子とセックスできねーぜ!』って言って、
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
って、俺たちのチンコをしごくんだぜ!」
そういいながら、津島君は、前にあるダビデ像のホーケーチンコに右手を添えて、それをまるで自分のチンコのように、シコシコ、摩擦し始めてしまうのだった。
津島君のそのエロいセンズリの手の動きに、寺田君も手塚君も、真っ赤な顔をして、すでにスクールパンツの中のピーナッツの大きさにも満たないホーケーチンポは、ムクっとその鎌首をもたげ、ビンビン怒張し始めていた。田中君は、ニヤニヤしながら、
「裕二、それで、ドピュって発射したくなったら、どうなるんだ?」
と、津島君をさらに乗せるように、話の先を促す。
「それでさー、オレの後ろでシコシコしてくれた先輩はさー、主将の山岡さんでさー、先輩ったら、オレのチンコつかむ前に、俺にさー、『裕二、オレの右手の摩擦係数は1.99999だから、気合入れて我慢しろよ!!』って言って、
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
だぜ! だからさー、ほんとキツかったぜあの時は・・・それでさー、ガマンできない時はだな・・・先輩に許可もらってドピュ!ドピュ!って男らしく前に発射するんだ!!」
寺田君も手塚君も、そして、その話が初めてではない田中君も、口々に、
「サッカー部、おまえら卑猥すぎるぞ!!」
「裕二、お前のシコリ方、サイコーに卑猥だ!!」
と言って爆笑するのだった。
一方、塚田君は、「摩擦係数」の物理的意味を理解しており、津島君が言った1.99999という数値に、思わず吹き出しそうになるのを必死で堪えていた。そして、塚田君は、
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
と、レプリカ・ダビデ君のホーケーチンコを摩擦する津島君の卑猥な右手の動きを、興味津々で凝視するのだった。津島君のダビデ像のチンコをいじるその右手の動きは、センズリ覚えたての若き雄猿のそれが醸し出すのと同じような野性味であふれていた。
ああ、「栴檀は双葉より芳し」とはまさにこのことなのか・・・。津島君は、この時、図らずも、男子校の保健体育の教諭としての役割を立派に果たしていたのである。なぜなら、当時の明和学園の中2生では一番の晩生(おくて)であった塚田君に性教育を施していたからである。
ハカセとあだ名され、クラスメートの誰もが博識と認める図書館男子の塚田ではあったが、この時、「ひとりH」のやり方をまだ覚えていたなかったのである。もちろん、図書館で調べて、「男子の手淫は、陰部を摩擦することにより行う」ということは理屈として知っていたのだが、具体的にどう摩擦するかまではイメージがわいていなかったのである。
そして、ダビデ像をつかった津島君の「男のオナニー・デモンストレーション」によって、塚田君は、中2にして、「ひとりH」のやり方を覚え、その日早速、図書館に隣接した男子便所の大便個室で、生まれて初めてシコッたのである。津島君のレプリカ・ダビデ君のホーケーチンコをシゴく、あの卑猥な手の動きを思い出しながら・・・。
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
田中君、寺田君、塚田君の「卑猥だ!」の賞賛の声と爆笑に、津島君は、「おっ!受けてるな!」と思い、気をよくして、ますます調子に乗ってくる。そして、
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
と、レプリカ・ダビデ君のチンコを、今までに増して、右手で早く激しくシゴき始めるのだった・・・。
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
シコ!シコ!シコ!シコ!シュイ〜ン!
「あっ!」
「あっ!」
「あっ!」
「あっ!」
それは津島君が、レプリカ・ダビデ君のホーケーチンコ・オナニーをフィニッシュしようとしたその時だった!!レプリカ・ダビデ君のチンコは、津島君の扱きのその摩擦力の強さに耐えられなくなったのである!!
ポロッ!
「あっ!まずい・・・チンコが・・・」
そう、石膏でできたレプリカ・ダビデ君のホーケーチンコが、ポロっと、もげてしまたのである!!
その時だった。
「コラ!!おまえら、そこで何やってんだ!!」
との怒号が、美術室の入口の方から、教室内にとどろいたのである!!
8 これは芸術を愛する人に対する冒涜(ぼうとく)だ!許せん!
津島君、塚田君、田中君、寺田君、手塚君の5人は、ギョッとして、美術室の入口のドアの方をみるのだった。
そこに立っていたのは、まるで五月人形の鍾馗(しょうき)様のような風貌をした背の高い教師と思われる中年の男だった。そして、その男は、津島君たち5人のことをものすごい形相で睨みつけているのだった。
「イ、イエローカードじゃない・・・初めてみるセンコー(先公)だ・・・」
津島君は、そう思いながら、右手に持っていたレプリカ・ダビデ君のもげてしまったホーケーチンポを右手のひらでギュッと握りしめると、それを隠すように、両手を後ろへ回すのだった。

「おまえら、そこで何をしているんだ!掃除はもう終わったのか?」
そう言いながら、鍾馗様のようなその男は、教室に入り、ゆっくりと津島君たちのいる方へと歩いてくる。左手には杖を持っている。どうやら右足に怪我でもしているらしい。
津島君たちは、背筋がゾクッとするような薄気味の悪さを感じ、ゴクリと生唾をのみ、その男と目を合わさないように下を向いてしまうのだった。そして、その男がゆっくりと自分たちの前へとやってくると、あたりに、プゥ〜ンと、酒の臭いが漂ってくるのだった。
「うわぁ・・・くせぇ・・・このセンコー、学校で酒飲んでる・・・本当に、センコーなのかな・・・」
津島君はそう思って、もしかするとすぐに逃げた方がいいかもしれない、それとも、デカい声を出して誰かを呼ぶべきなのかと迷うのだった。そして、津島君が、他の4人に、「おい!逃げろ!」と言おうとしたその時だった。
「おい!そこのチビ!後ろに何を隠しているんだ!」
と言って、その男は、左に持った杖で、津島君の方を指すのだった。
津島君は、すかさず、
「えっ・・・ボ、ボクはチビじゃないです!津島裕二です!」
と言って、その男の目をみて、キッと睨み返すのだった。
津島君のその目力に、思わずたじろぐ男。しかし、津島君のその睨みをはねのけるかのように、その男は、
「そんなことは聞いとらん!後ろに隠したものをオレに見せるんだ!」
と、怒鳴るのだった。
その男の真剣な声色に、津島君もこれ以上反抗してはマズいと思ったのか、後ろへまわしていた右手を前にもってくると、その男に見せるように、レプリカ・ダビデ君のもげてしまったホーケーチンコをその男の前に差し出すのだった。
「ご、ごめんなさい・・・ボ、ボクがこわしました・・・で、でも、わざとじゃないです・・・」
津島君は、神妙な面持ちでその教師と思われる男に謝ると、ペコリと頭を下げるのだった。
「なんだと!!ダビデ像のペニスにいたずらして壊しおって、わざとじゃないだと!!ふざけるな!!立考(りっこう)だ!!おまえら5人全員、後ろの壁に向かって立って反省しろ!!」
そういうと、その男は、津島君からレプリカ・ダビデ君のもげてしまったホーケーチンコを奪うようにして取り上げると、それをズボンのポケットに無造作に放り込み、ゆっくりと教壇の方へ行き、ちょっと背伸びすると、黒板の上に隠すように置いてあった青い「ケツピン棒」を右手でつかみ取るのだった。
トン!トン!トン!トン!トン!
その先生が、左手にもった杖で、美術室の床をつく音が迫ってくる。
「立考(りっこう)」とは、「ケツピン棒」と並ぶ明和学園における名物指導法の一つで、教室や廊下の壁に向かって生徒を立たせ、己の怠惰や悪行についてしっかりと考えさえ反省させることである。もちろん、壁の方を向って立てば、おケツは丸出しである。「立考」中の反省の態度がなっていないと、いつでも、立考指導した教師が持つケツピン棒が尻に飛んでくるわけであり、当時の明和学園において「立考」は、「ケツピン」の前奏曲的色合いもあり、「正座」よりも厳しい罰とされていた。ただし、2B担任の吉川先生は、いきなりケツピン指導をする方で、生徒指導法として、立考はあまり使わなかった。
立考を命じられた津島君たち5人は、自分たちの後ろに迫りくる杖の音に、再び、背中にゾクッとするような寒気を感じる。そして、怖そうなその男からケツピン指導されるかもしれないという予感をケツに感じ、ピクッピクッと両ケツペタを引き締めるかのように動かすのだった。
再び、その男の酒臭い息が、津島君たちの鼻を憑く。
「いいか!!ダビデ像にいたずらをするなど、芸術を愛する世界中の人々を冒涜しているに等しい!とりもなおさず、それは芸術に対する冒涜でもある!オレは、芸術を冒涜した者を絶対に許さん!!」
その男の説教を聞きながら、ハカセこと塚田君は、「えっ・・・そんな大げさな・・・」と思うのだった。
「よって、これから、オレは、この懲戒棒で、お前らの尻を、たっぷりと打ちのめしてやる!!」
そういうと、先生は、右手に持った青い「ケツピン棒」で、津島君たち5人が向き合っている壁を、津島君たちの顔の高さのところで、トン!トン!トン!トン!トン!と軽く突き、その「ケツピン棒」を津島君たちに見せつけるようにするのだった。その竹棒は、イエローカードこと吉川先生が持つケツピン棒とほぼ同じサイズだったが、青色のビニールテープがぐるぐると巻き付けてあり、吉川先生の竹棒とは色違いであった。
「最近のガキどもは、この棒のことを『ケツピン棒』などと下品な呼び方をするらしいが、オレがこの明和中学の生徒であったころは、『懲戒棒』と格調高き呼び名で畏れられていた!今日はこれからお前らに、オレの教室で、芸術を冒涜する行為をしたならば、どのような罰を食らうか、この懲戒棒でたっぷりと教えてやる!!ズボンとパンツを下ろせ!!」
「えぇーー」
先生のその言葉に、塚田君が思わず何とも言えない声を漏らすのだった。それを聞いた津島君は、「これはマズい!」と思う。もしここで、万が一にも、ハカセこと塚田君のご機嫌を損ねたら、定期試験の時、もうノートを貸してもらえなくなるかもしれない。もしそうなったら、津島君の通知表は、赤点のオンパレードだ。どうにかしてハカセこと塚田君のお尻だけは、ケツピン棒から守ってあげなければならない!!
「先生!!ダビデにいたずらしたのは、オレです!!ケツピンはオレだけにして下さい!!」
津島君は、あわてて、他の4人に対するケツピンのご赦免をその男に嘆願するのだった。
「このチビめ!生意気なことをほざきやがって!ダメだ!5人の連帯責任だ!!全員早くズボンとパンツを下ろせ!!」
「あぁ・・・」
男のその言葉に、立考中の5人は、何とも言えない切ない溜息をもらす。
「チェッ!」
津島君が舌打ちをして、その男に、どうにか抗(あらが)おうとするが、カチャカチャカチャと、隣で塚田君が学ランズボンのベルトを緩め初めてしまう音を聞いて、津島君も観念するしかないと思うのだった。
津島君は、白のサッカーパンツと白ブリーフを下ろし、田中君はやはりカチャカチャと野球部のユニズボンのベルトを緩め始める。そして、バレー部の寺田君は、体育授業用の白短パンと白ブリーフを下ろし、テニス部の手塚君は、白のテニスパンツと白ブリーフを下ろすのだった。そして、塚田君が学ランズボンと白ブリーフ、田中君が野球のユニズボンと白ブリーフを下ろす。田中君は、コーチや先輩からのケツバット対策として、白ブリーフのケツのところに、白い雑巾を一枚仕込んであり、それがボトンと哀しげに美術室の床に落ちるのだった。
これで5人全員、生ケツ丸出し。壁の方は、ホーケーチンコがフリチン状態。津島君たち5人は、美術室の壁に向って、まさに「フリチン立考」状態で、その男の青い「ケツピン棒」が、おケツに飛んでくるのを待つのだった。津島君たちのホーケーチンコには、チンカスが相当に溜っているのだろうか、美術室には、ツ〜ンと栗の花の青臭い臭いが漂っていた・・・。
「フフフ・・・よーし、誰のケツからひっぱたくかな・・・おまえら、覚悟しろよ・・・今日はおまえらのケツがこの棒と同じく真っ青になるまで、打ちのめしてやる!!」
そういいながら、右手に持った青いケツピン棒で、ブン!ブン!と空を切る男。その音は、津島君たち5人の耳にも不気味に届いていた。塚田君と手塚君は、恐怖で、思わず、ギュッと両目をつむるのだった。
しかし、その時だった。
「黒岩先生!!その5人への罰は、私に、お任せください!!」
と、津島君たち5人の耳に、聞き慣れた、それはもう、涙が出るほど懐かしいとも思われる、よく通る声が飛び込んできたのだ。2年B組の津島君たちの担任である、イエローカードこと吉川先生の声であった。
美術室に入ってきた吉川先生の右手には、いつもの黄色いケツピン棒が握られていた。第一美術室の掃除完了の報告がいつまで待ってもないので、吉川先生が心配になり、体育館職員室から第一美術室へやってきたのだ。
津島君たち5人に「フリチン立考」を命じたその男は、明和学園・芸術科・美術担当の黒岩幹(くろいわ かん)先生だった。黒岩先生は、大正3年生まれの45歳。明和学園の前身である旧制・明和中学の卒業生で、吉川先生と同じく明和学園のOB先生であった。あだ名は「よっぱらい」で、ケツピン棒カラーは青(ブルー)である。黒岩先生は、当時、高校生クラスのみを担当していたため、津島君たちは、まだその顔を知らなかったのだ。
「なに!!」
吉川先生のその声に、黒岩先生はギョッとしたように振り向き、美術室に入ってくる吉川先生の方を見るのだった。黒岩先生にとって、17歳年下の吉川先生は、明和学園の後輩であり、教え子でもあった。
「黒岩先生、その5人は、私の担任クラスの生徒です。罰は私が与えます!」
「何だ・・・お前のクラスのガキどもだったのか・・・どうりで下品なわけだ・・・」
黒岩先生のその嫌みに、吉川先生は、ちょっとムッとしたような顔をして、
「この5人が、先生のご機嫌を損ねるようなことを何かしでかしたのでしょうか?」
と、やや反抗的な声色で、黒岩先生に質問するのだった。
「これを見ろ!!」
そういうと黒岩先生は、ズボンのポケットに放り込んであったレプリカ・ダビデ君のもげてしまったホーケーチンコを吉川先生に見せるのだった。
レプリカ・ダビデ君のもげてしまったホーケーチンコを見て、思わず吹き出しそうになるのを必死で堪える吉川先生。吉川先生が明和中学の生徒だった時代からあるこのレプリカ・ダビデ君。このレプリカ・ダビデ君のホーケーチンコは、吉川先生が生徒だった時代から、やんちゃな生徒たちにいたずらされ、その手垢で常に黒光りしており、しばしば、ポロン!ポロポロポロン!ともげ落ちては修復されていたのだった!!もちろん、吉川先生も、そのいたずらで、若き日の黒岩先生からケツピン指導を受けた経験があったのだ。
吉川先生は、自分のにやけた顔を隠すかのように、
「も、申し訳ございません!!」
とすぐさま大声で言って、腰を90度近くのまで曲げて、深く頭を下げるのだった。そして、
「この5人は、私がこの懲戒棒で、しっかりと指導しておきますので、ここのところは、担任の私にどうかお任せください!!」
と、きっぱりと言うのだった。
津島君たち5人にとって、担任の吉川先生のケツピン指導も、それはそれで嫌なことではあったが、黒岩先生の青いケツピン棒で剥き出しのケツをぶっ叩かれるよりはマシだと思い、なぜかホッと安心した気持ちになるのだった。
「チッ!おまえも偉くなったもんだな・・・オレの手をさんざん焼かせおったおまえが、一丁前に、ここの教師になるとはな・・・」
「はい!明和中学時代に先生から懲戒棒で受けたご指導は、私の尻にしっかり刻み込まれております。ありがとうございます!」
フリチン立考をしながら吉川先生のその言葉を聞いていた津島君たち5人は、「イエローカードもケツピン棒、食らったことあるんだ!」と思い、いままでよりもちょっとだけ担任の吉川先生に対する親近感が増してくるのだった。
「チッ!今回だけだぞ!お前の顔をたててやるのは!こいつらに二度と下品ないたずらをせんように、しっかり指導しとけ!」
「はい!ありがとうございます!」
黒岩先生は、不満げな顔をしながらも、左手には杖、右手には青いケツピン棒を持って、ゆっくりと美術室の入口の方へと歩いていくのだった。そして、美術室の入口のところで立ち止まると、振り向きもせず、
「吉川!!指導が終わったら、オレのところへ来い!壊れたダビデ像のことで話がある!」
と言って、第一美術室の隣の美術準備室の方へ、コツ!コツ!コツ!と杖の音を鳴らしながら、消えていくのであった。
黒岩先生の命令に、吉川先生は、
「はい!必ずうかがいます!」
とデカい声で返事をして、黒岩先生が美術準備室の扉を開けて、それが閉まる音が聞こえてくるまで、深々と頭を下げ続けていたのだった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「おまえら、パンツとズボンを上げていいぞ!こっちを向くんだ!」
黒岩先生がいなくなった美術室で、吉川先生は、「フリチン立考」をしている津島君たち5人にそう言って、「立考」を解いてやるのだった。そして、下を向いたままの津島君たちに5人に、
「早く教室の窓を閉めて、掃除を終わらせろ!掃除が終わったら、5人とも体育館の職員室へ来ること!いいな!逃げんじゃねーぞ!」
と言い渡し、黄色いケツピン棒を右手でブンブンと振りながら、どこか機嫌よさそうに、第一美術室を出ていくのだった。
津島君たち5人は、「はい・・・」と元気なく返事をし、担任の吉川先生のそんな後ろ姿を不安そうな表情で見つめながら、
「あーあ・・・体育館職員室でケツピンか・・・・」
と覚悟を決めるのであった。
9 体育館職員室での立考(りっこう)
「立考!!!おまえら5人、向こうの壁に向かって立って、しばらく反省しろ!!」
体育館職員室で、自分の前に立つ津島君たち5人に、吉川先生は、厳しく命令する。
「はい・・・」
そう返事をして、体育館職員室の一番奥の先生たちの机が置かれていない壁の前へと、重い足取りで向かう津島君たち。
「いきなりケツピンじゃない・・・めずらしい・・・」と、寺田君。
「チェッ、早く終わらせてほしいよ・・・でないと、部活、遅刻どころかおわっちまう・・・・」と、手塚君。
「あ、マズい・・・パンツにぞうきん入れ直すの忘れてた・・・あ、ぞうきんも忘れた・・・」と、野球部の田中君。
田中君は、ケツバット対策用にパンツのところに家から持ってきた雑巾を仕込んでいたのだが、美術室での「フリチン立考」でその雑巾を美術室の床に落としてきたままだったのだ。その白い雑巾は、うっすらと田中君の茶色いウン筋つきだった・・・。
「イエローカード、あのヒゲのセンコーのマネしてるのかな・・・それとも、すげー、怒ってるのかな・・・」と、津島君。
「お尻叩かれちゃうよ・・・どうしよう・・・すごく痛いのかな・・・でも、津島君といっしょでよかった・・・」と、ハカセこと塚田君。
イエローカードこと吉川先生の「立考」の罰は、30分近くに及んだ。その間、体育館職員室は、吉川先生以外の体育の先生が、出たり入ったりしている。
「よぉ〜、おまえら、何やらかしたんだ?」
と、津島君たち5人をからかっていく先生もいた。
「先生、あいつら、何やらかしたんですか?先生が、立考させるだなんて、めずしいッスね?」
と、体育担当の辻岡武志(つじおか たけし)先生が、ニヤニヤしながら、吉川先生に聞いてくるのだった。
辻岡先生は、吉川先生よりも2歳後輩で、主に高校生クラスの体育を担当している。やはり明和学園出身のOB先生で、ケツピン棒カラーは、緑(グリーン)だ。吉川先生よりも背がかなり高く、あだ名は「ノッポ」。バレーボール部の監督兼顧問もつとめていた。
辻岡先生のその質問に、吉川先生は、
「美術室でダビデのチンチンポロリだ・・・」
とニヤニヤして辻岡先生に言うのだった。
「えっ!本当ですか?!そりゃ、傑作だ!ワハハハ!!」
と、大爆笑。さらに、
「そういえば、先生・・・先生がやらかした時も、たいへんでしたよね!懲戒棒でみっちり指導されて・・・たしか、あの時は、タマまでとれちゃって、あの彫刻、去勢状態でしたよね!!」
と、辻岡先生は調子に乗って、吉川先生が、やはり中学時代、美術室のダビデ像のおチンチンを壊してしまい、黒岩先生から大目玉を食らった時のことを暴露しようとするのだった。
それには、さすがの吉川先生も、耳まで真っ赤になって、
「コラッ、そのことは、こいつらの前では秘密だ!」
と小声で言って、辻岡先生の丸刈り頭を平手で軽く叩こうとするしぐさをするのだった。
「あっ、すいません・・・」
と、悪戯っぽい後輩の笑みを浮かべて謝る辻岡先生。そして、
「おっ、うちの部の寺田がいるな・・・ちょっと、からかってやるか!」
と、辻岡先生はつぶやくように言うと、右手に緑色のケツピン棒を持って立ち上がり、津島君たち5人が「立考」している壁の方へ行くのだった。
「よぉ!寺田!ここで何やってんだよ・・・」
寺田君は、まさかの部活の顧問登場に、そんなこと聞くなよといった表情をして、
「りっ、立考です・・・」
と、真っ赤な顔で答えるのだった。
「フフフ、吉川先生、すげー怒ってるぞ・・・まあ、覚悟しとくんだな・・・」
そういうと、辻岡先生は、右手に持った緑色のケツピン棒で、寺田君の薄汚れた体育白短パンのプリっとしたお尻を、
パチン、パチ〜ン!
と軽く2発叩いて、職員室の後ろの扉から出て行ってしまうのだった。
辻岡先生に叩かれた短パンのケツを右手でさすりながら、寺田君は、
「あぁ・・・イエローカードのケツピンは、あれよりうんと痛いんだろうな・・・」
とつぶやくように言うのだった。
辻岡先生が出ていくと、体育館職員室にいる先生は、吉川先生一人だった。
「そろそろだな・・・」
そう言いながら、吉川先生は、時計をみると立ち上がり、右手に黄色いケツピン棒を握りしめて、津島君たち5人が「立考」している壁の方へと行くのだった。
「よし!おまえら、全員、回れ右だ!こっちを向け!」
と、津島君たちに命令する吉川先生。右手には、黄色いケツピン棒が握られていた。
津島君たちは、吉川先生の方を向いても、下を向いたまま、しかし、吉川先生の持つケツ叩き用の竹棒が気になるのか、それにチラッチラッと視線を向けていた。
そんな中、津島君がすっと顔を上げ、吉川先生の顔をみると、
「先生!彫刻をこわしたのはオレです。ケツピンはオレだけにしてください!」
と、懇願するように言うのだった。
「おぉ、チビスケ、おまえはそんなに俺からケツを叩かれたいのか!だったら、叩いてやってもいいけどな・・・フフフ」
と、吉川先生がニヤニヤした顔で言う。吉川先生の声色はやさしかった。
その吉川先生の反応に、
「えっ・・・先生、ケツピンしないんですか?」
と、田中君。
「そうだな・・・今日はケツピンはなしだ!」
「おぉ!!」
「やった!!」
「助かった!!」
津島君たちから思わず歓声が上がる。しかし、それをたしなめるかのように、吉川先生は、すこし厳しい声になって、
「今回だけだぞ!今度またやらかしたら、承知しねーからな!それから、あの美術室は、高校生用の教室だ。あの教室の備品が壊れて、一番迷惑するのは、お前たちの先輩方だ!だから、今後は、あの教室で絶対にいたずらはするな!いいな!わかったか!」
と言うのだった。
「はい!」「はい!」「はい!」「はい!」「はい!」
と、うれしそうに元気に返事をする5人。ケツピン指導なしに、5人ともホッと一安心だったのだ。
「よし!解散!行っていいぞ!」
と吉川先生。
それに、「ありがとうございました!」「失礼します!」と口々に挨拶して、体育館職員室を出ていく津島君たち5人だった。
体育館職員室に残った吉川先生は、やれやれといった表情をして、
「ったく、アイツら、手を焼かせやがって・・・さてと、気が重いが、美術準備室へ行って『カンカン』と話をつけてくるか・・・」
とつぶやくと、体育館職員室を出て、校庭から見て、体育館の裏手にある芸術科校舎へと向かうのだった。
吉川先生の恩師でもある黒岩幹(くろいわ かん)先生。吉川先生が明和中学の生徒だった時代のあだ名は、「よっぱらい」ではなく、「カンカン」だった。それは、黒岩先生の名前に由来するようにも思えるのだが、本当のところは、吉川先生が生徒の時、鎌倉への修学旅行中、宿泊先の宿舎の宴会場で行われた「かくし芸大会」で、生徒たちの前で、
「いいか、これがパリ・モンマルトルのキャバレー・ムーランルージュで行われている本場フランスのフレンチカンカン・ダンスだ!よくみとけ!」
といって、真っ裸のフリチンで「フレンチカンカン」を踊ったことがその由来であったらしい。黒岩先生は、帝都美術学校での学生時代、本場おフランスはパリに留学した経験があり、留学中は、社会勉強と称して、留学仲間とモンマルトルのキャバレーに夜な夜な遊びにいったことがあったのだ。旧制・明和中学時代の黒岩先生は、懲戒棒での指導は容赦なくちょっと怖いが、普段は豪快で明るい、生徒たちには人気の先生であり、学校で酒を飲むことなどなかったのである・・・。
・・・・・・・・・・・
体育館から校舎の方へと戻る途中、津島君が、塚田君に、
「ハカセ・・・おまえを巻き込んぢまって、スマン・・・」
と謝り、ペコリと頭を下げるのだった。
塚田君は、ちょっとどまったような顔をするも、
「津島君がボクにあやまらなくても・・・いいよ・・・それよりも、ありがとう・・・」
と言うのだった。
「なんでハカセが、オレに礼を言うんだよ!?」
「えっ・・・な、なんでも・・・た、ただ・・・」
「やっぱり、おまえ、変なヤツだな・・・まあ、そんなことどうでもいいけど・・・あ、今日の3時間目の幾何の授業、ねむくてさー、あとでノート貸してくれる?」
「う、うん!もちろん!」
「サンキュ!じゃあな!」
お調子者の津島君は、しっかり、ハカセこと塚田君から、数学の板書ノートを借りる約束をとりつけて、校庭を走って去っていくのだった。
いつものように図書館に向かう塚田君。
「で、でも・・・津島君と一緒だったら、吉川先生からお尻叩かれてみたかったな・・・」
とつぶやくように言うと、頬をポッと赤らめる。その時、塚田君の茶色い染み付きスクールブリーフのなかの、まだまだ皮が剥けきれないピーナッツのようなおチンチンは、ビンビンに怒張していたのだった。
10 常連登壇!!
キンコンカンコーン!カンコンキンコーン!
その翌日の水曜日。明和学園の木造校舎に、4時間目の終業を知らせる鐘が鳴っている。
津島君たちが所属する中学2年B組の教室では、中学2年C組担任で、数学担当の生方久男(うぶかた ひさお)先生(25歳)の数学(代数分野)の授業が終わろうとしていた。
生方先生はまだ教壇に立って、クラスに向かって何か告げようとしている。しかし、そんなことにはお構いなしに、一番前に座っていた津島裕二君は、鐘が鳴り始めると早速立ち上がり、体操服に着替え始める。
「コラ!津島!まだ授業は終わってないぞ!」
しかし、先生のそんな注意を無視するかのように、津島君は、ただ、
「ィ〜ス!」
と応答しただけで、着替えを続行している。
数学担当の生方先生は、明和学園出身のOB先生ではあるが、ケツピン棒は持っておらず、その年の中学2年の担任教諭の中では、生徒たちから一番やさしいとされていた先生だった。すなわち、津島君たち運動部所属のやんちゃな生徒たちからは、完全になめられていたのである。
生方先生は、「まったく、しようがねーなー」といった顔つきをすると、津島君の着替えが呼び水となってしまい、ざわつき始めている教室の生徒たちに、
「明日までに教科書第6章の章末問題をやっておくこと、いいか、これは宿題だからな!」
と大きな声で言うと、教科書、ノート、そして、閻魔帳を教卓からとり、2Bの教室をでていくのだった。
生方先生が教室から出ていくと、待ってましたとばかりに、津島君が教壇に上がるのだった。津島君の姿をみて、教室では、大爆笑が起きる。
教壇に上がった津島君は、上は学校指定の白の体操服の上着だったのだが、下は、なんと、スクールブリーフ一丁だったのである!
「全体的にさー、もっと机下げろよ!そうそう、ここらへんがイエローカードが右足つくとこだな!」
クラスメートが自分の姿を見て大笑いしていることなどどこ吹く風、下は白ブリ一丁の津島君は、津島君が間もなく「登壇」する舞台造りのために、クラスメートたちに指示を出すのだった。
その舞台とは、もちろん、イエローカードこと吉川先生担任クラスの昼のST時の名物である「昼礼ケツピン」の舞台であった。吉川先生のクラスでは、その日の1時間目の授業に正当な理由なく遅刻をした生徒のパンツ一丁のケツを、吉川先生の黄色いケツピン棒でバチンと1発叩いて指導することがお約束となっていた。
遅刻した生徒は、朝、校門のところで待ち構えていた生活指導の教諭によって、遅刻の理由を問わず生徒証を一時的に没収されてしまうのだった。そして、吉川先生の担任クラスでは、昼のSTの際に、吉川先生がその遅刻に正当な理由がないと判断すれば、バシッと1発ケツピン指導が敢行された後、生徒証が返却されるのであった。
毎週、水曜日は、津島君が所属するサッカー部の朝練オフ日。毎週、水曜日は、サッカー部員たちにとって、遅刻要注意日だったのだ。
そして、津島君は、中2に進級してから、水曜日は、毎週、寝坊して遅刻し、昼のSTの時は、教壇に上がり、黒板に両手をついて、スクールパンツ一丁のケツを後ろに突き出し、吉川先生からケツピン指導をバシッと1発いただいていたのだ。
「裕二!おまえ、2年生になってから、これで遅刻、何回目?」
と、野球部の田中君がニヤニヤしながら聞いてくるのだった。再び、クラスから大爆笑が起きる。
「知らねー、そんなことよりさー、今日のサッカーの試合、がんばろうぜ!」
と、田中君向って言うのだった。
「おお!」と、それに応える田中君も、学校指定の白の体操服に着替え始めるのだった。
その日の午後、5・6時間目は、中学2年A組と合同の体育の授業であった。当時は、1クラス約50人の生徒がいた時代である。2クラス合同だと約100名近い生徒が、東京都中野にある明和学園の決して広くはない校庭で授業をするのだから、なかなか壮観であった。
特に、その日の体育の授業は、2年A組、B組対抗のサッカーの試合であり、1クラス何班かに分かれて、試合をする授業であった。そのため、サッカー部所属である津島君は、いつも以上に張り切っており、「昼礼ケツピン」の儀式は、自ら進んでケツを出し、嫌なことは早く忘れて、体育の授業で行われる楽しいサッカーの試合へと気持ちを転換したかったのである。
しばらくすると、吉川先生が、いつも通り、黄色いケツピン棒と閻魔帳を持って、教室に入ってくる。吉川先生は、いつも通り、白の体操服の上下で、上は白のポロシャツのような半袖体操上着で、下は白のトレパンであった。体操上着にくっきり浮き出た白のランニングシャツのラインと、トレパンのケツのところに浮き出た白のブリーフラインが印象的だった。吉川先生は、ステテコパンツ世代だが、学校の新スクールパンツである白ブリーフの方が機能的であると考え、明和学園の購買部で、白ブリーフを購入し、常用していたのだ。
教室に入ってきた吉川先生は、すでに教壇の上に立っている、毎週水曜日のレギュラー・津島裕二君の下はパンツ一丁の姿と、教壇と最前列の生徒たちの机の間にできた空間をみて、ニヤニヤ笑いながら、
「おー、チビスケ、今日はヤケに準備がいいな!」
と、からかうように言うのだった。
津島君は、待ってましたとばかりに、
「ィ〜ス!」
と返事をすると、吉川先生が何も言わないうちに、両足をやや開いて、黒板に両手をつくと、白ブリ一丁のケツを、後ろへプリッと突き出し、
「寝坊して遅刻しました!お世話になります!」
と、デカい声で言うのだった。
大爆笑の教室。吉川先生もニヤニヤしながら、
「よし!ちょっと待ってろ!」
と言うと、持っていた黒の閻魔帳と津島君の生徒証を教卓の上に置き、黄色いビニールテープがグルグルと巻かれた竹棒、通称・ケツピン棒を右手に持って、黒板に両手をついて、後ろにケツを突き出している津島君の左横へとやってくるのだった。
そして、吉川先生は、やけに機嫌よさそうに、教壇から一旦降りると、
「この寝坊助め・・・毎週のように遅刻しやがって・・・ケツにビシッと気合を入れてやるからな・・・」
と言いながら、左足を教壇の上に置くと、津島君の白ブリーフ一丁のケツに狙いを定めて、右手に握った黄色い笞(ムチ)で教室の天井を突くかのように、高く振り上げるのだった。
「く、くる・・・」
津島君は、そう思って、ケツをさらにギュッと後ろへ突き出し、頭をやや下げて、奥歯をくいしばり、両目をギュッと閉じて、吉川先生のケツピン棒がケツに噛みつく時の熱い衝撃に備えるのだった。「昼礼ケツピン」常連の津島君であっても、先生が自分の後ろで、自分のパンツ一丁のケツに狙いを定めてケツピン棒を振り上げる気配を感じるこの瞬間に慣れることはできなかった。
「よし!いくぞ!」
「はい!お世話になります!」
吉川先生にとっても、昼のケツピン指導常連の津島君のおケツは、叩きやすいらしく、それはもうあうんの呼吸だった。吉川先生は、振り上げていた黄色い竹棒を、津島君のケツめがけて、思い切り腰を入れて振り下ろすのだった。
ブン!!
と、笞が空を切る音が教室に鈍く響いたかと思うと、
ビシッ!!
と、ケツピン棒が津島君の白ブリのケツに着地する音が、教室にいる生徒たちの耳に飛び込んでくるのだった。
「おぉーーーー!!」
「いまのは入ったーーー!!」
と、教室からはまるで感嘆するような声が響いてくる。
「いっ、いてぇ・・・」
とつぶやくような声をもらす津島君。しかし、次の瞬間、津島君の
「お世話になりましたーーー!!」
の気合の入った元気でデカい声が教室に響くのであった。
教室からは、再び、
「おぉーーーー!」
という声とともに、拍手をする生徒たちもいる。
津島君は、黒板から両手を離すと、真っ赤な顔で。
「いってぇ・・・」
と言いながら、ジリジリと熱く焼けるような痛みがひろがるブリーフのケツを両手で必死にさするのであった。
その姿をニヤニヤしながら見ている吉川先生。しかし、その日の「お昼のケツピンショー」はそれで終わりではなかったのだ。
「おい、チビスケ!今日は、もう一丁指導してやるから、もう一回、黒板に手をついてケツを出せ!」と吉川先生。
「えっえー!な、なんでですか!」と、ケツを両手でさすりながら、真っ赤な顔のまま口を尖らす津島君。
「来週の分だ!おまえ、どうせ、来週の水曜日も遅刻するつもりだろうが?どうなんだ?」
「えっ、来週は遅刻しないように・・・」
「ウソつけ!」
「そ、そんなこと、来週にならないとわからないじゃないですか!!」
「オレは、来週の水曜日、出張でいないんでな・・・その分の指導だ!」
「えーー、きったねぇー」
津島君は、真っ赤な顔で、まだケツをさすりながら、不満そうな表情を浮かべている。
そんな津島君に、クラスの連中は、今回はあまり同情的ではなかった。あまりにも「ケツピン指導」慣れして、毎週水曜日に当然のごとく遅刻を繰り返す「常習犯」の津島君に、クラスメートたちは、「アイツ、ちょっとズルいよな・・・」と思い始めていたのだった。そして、吉川先生の津島君への「ケツピン指導もう一丁」の宣言をしごく当然のことのように思う生徒が多かったのだ。
「もう一丁!」「もう一丁!」
「ケツピン!」「ケツピン!」
「ケツ出せ!」「ケツ出せ!」
と、クラスの連中が、ニヤニヤしながら、手拍子打って囃し立て始めるのだった。
これには吉川先生も苦笑い。不満そうな顔をしている津島君に、
「オラ!コイツらも待ちかねてるぞ!グズグズ言わずに、男らしくさっさと黙ってケツを出せ!」
と、ニヤっとして命令するのだった。
津島君も観念したのか・・・不満そうな顔をしつつも、
「ィ〜ス!」
と返事をすると、両手でケツをゴシゴシっとこするようにもう一度さすってから、黒板に両手をつき、両足を開いて、
「もう一丁、お世話になります!」
と言うのだった。
「よし!いくぞ!」
と吉川先生の言うが早いか、
ブン!!
と黄色い笞が空を切ると音とともに、
ビシッ!!
と、ケツピン棒の2発目が、津島君の白ブリーフのケツを強襲する音が教室に響き渡るのだった。
「おっ!今のケツピン、すげぇ・・・」
その音を聞いて、津島君の「お昼のケツピンショー」には全く興味を示すことなく、お袋さんがこしらえくれた弁当に顔をうずめていた、一番後ろに座る野球部の石井健介君も、思わず昼飯を食うのをやめ、「おっ!」と弁当から顔を上げるのだった。
「いっ、てぇーーーーー!!!」
白ブリ一丁のケツを後ろにプリッと突き出していた津島君は、吉川先生のケツピン棒が、ケツのど真ん中に着地した刹那、反射的に黒板から両手を離し、両手で白ブリのケツを必死でさすり始める。そして、挨拶するのも忘れて、その場でピョンピョンと飛び跳ねるのだった。「お昼のケツピンショー」の常連である津島君にとっても、ケツピン指導・連続2発は、チトきつかったようだ。
その滑稽で、ちょっと格好悪い、津島君の姿に、2Bからは爆笑が起きる。一方、野球部の田中君は、
「おい!裕二!挨拶だ!挨拶しろ!」
と、津島君に助け舟を出す。ケツピン指導のあと、「お世話になりました。」の挨拶を忘れると、ケツピン指導やり直しとなっても文句はいえないのだ。
吉川先生は、自分の厳しいケツピン指導で、2Bで一番のやんちゃ坊主のケツにキツイお灸をすえることができたと確信したのだろうか、ニヤニヤと満足そうな笑みを浮かべて、津島君のいまにも泣きそうな顔とケツを必死でさする様子を眺めている。
そんな吉川先生の方を向いて、津島君は、
「お、お世話になりました!」
とあわてて挨拶すると、ペコリと頭を下げるのだった。
そんな津島君に、吉川先生は、さらにショッキングなことを言うのだった。
「おっと、チビスケ、言い忘れるところだったぜ・・・今日の体育の時間、おまえは、『見学』扱いだ!」
「えっ!どういうことですか!!今日の体育は、サッカーの試合じゃないんですか!」
「そうだサッカーの試合だが、お前は見学扱いとし、今日の5、6時間目は、体操服を着たまま、第一美術室へ行くこと!いいな!」
「えっ!そ、そんなー。サッカーの試合、楽しみにしてたんですよ!」
吉川先生の指示に、まだまだ不平そうな顔をしている津島君に対して、吉川先生は、
「ゴタゴタ言うな!これが美術室の備品を壊したおまえに対する罰だ!!わかってるな!」
ときっぱり言う。
吉川先生のその言葉に観念したのか、津島君は、まだ真っ赤な顔で不満そうな表情を浮かべてはいたが、さらに口答えすることもなく、ケツピンを2発食らって痛む尻を力なくさすりながら教壇からおり、白の体育短パンをはくと、自分の席にそぉーとつくのだった。
「ちくしょー!!ケツいてぇーー!!」
自分の席についた津島君は、吉川先生にも聞こえるような大きな声でそう言うと、弁当箱を開けて、お袋さんがこしらえてくれた「日の丸弁当」に食らいつくのだった。
そんな津島君の姿に、吉川先生は苦笑い、教室は大爆笑に包まれるのだった。
11 高校生ケツピン指導 〜 西女(にしじょ)のスカート下からめくれ、明和(めいわ)のブリーフ上からめくれ! 〜
水曜日午後。第一美術室では、6C(高校3年C組)の授業が行われようとしていた。授業を担当するのは、美術の黒岩幹(くろいわ かん)先生。午後の5・6時間目2コマを通して行われる高3の美術の実習授業。その日の題目は、「石膏デッサン」。石膏像をモチーフに、鉛筆デッサンの基礎を学ぶ授業だった。もちろん、その日の石膏デッサンのモチーフは、男子校では大人気のミケランジェロ作「ダビデ像」のはずだったのだが・・・。
「ここにいるチビが、きのう、後ろにおいてあるダビデ像のペニスを壊しおった!!そのため、ダビデ像は、現在、修復中で、使用不可である!!」

黒岩先生は、教壇の上、自分の横に立っている津島君を睨みながらそう言うと、右手に持った青いケツピン棒で、教室の後ろ隅に置かれた石膏のレプリカ・ダビデ像を指すのだった。
学校指定の白の体操服上下を着た津島君は、教壇の上で、ちゃぶ台ほどの高さがある木製の台の上に立たされていた。その台の上には、昨日、石膏のレプリカ・ダビデ像が置かれていたのだ。津島君の鼻を、酒の臭いがツ〜ンと憑く。黒岩先生の息は、前の日と同じで酒の臭いプンプンであった・・・。
一方、6Cの生徒たちは、先生のその言葉に、一斉に後ろを向き、そのダビデ像を見て大笑いをする。ダビデ像の股間のところには、「修復中」と朱書きされたわら半紙が張ってあったのだ。
明和学園の美術の授業では、美術室で行われる製作実習に出席する際は、「実習着」として、体操服上下(下は短パンでも可)が指定されていた。学校指定の白の体操服上下を着た6Cの生徒31名が木の丸椅子に座っており、その前には各々イーゼルが置かれていた。これから鉛筆デッサンの実習に取り組むのであった。
明和学園は高校からの入学がない完全・中高一貫6年制の男子校であったが、中学がA〜Eの5クラス体制であるのに対し、高校からは8クラス体制となり、1クラスの生徒数は、30〜35名となるのである。
6C(高校3年生)の生徒たちは、もちろん、黒板の前に立たされている津島君と同じ学校指定の白の体操服上下を着ている。しかし、6C生徒たちの体格は、すでに成人男子のそれに近づいており、6月で下は白短パンという生徒も多い中、短パンからヌッとでた両脚の脛(すね)が野郎臭い剛毛で覆われている生徒も多かった。
黒岩先生は、教壇の上、自分の横で、ちゃぶ台のような台の上に立つ津島裕二君に、
「よし!チビ!先輩たちに謝るんだ!!」
と命令をする。そして、
パチ!パチン!
と、右手に持った青いケツピン棒で、軽く2発、津島君の白の体育短パンのケツを叩くのだった。
「いっ、痛いです・・・」
といって、津島君は思わず短パンのケツを引くしぐさをする。自分たちの前に立たされている、いかにもやんちゃそうな後輩のかわいらしくユーモラスなそのしぐさに、教室からは笑いが起こる。その笑い声は、低く野太く、中学2年生のクラスに響き渡る甲高い笑い声と比べたら、それはもうオッサンの笑い声と言っても大げさではなかった。
「おまえのケツが痛いかどうかなど誰も聞いとらん!!先輩方に謝るんだ!!」
バチン!!
と、黒岩先生はさっきよりもかなり強めに、青いケツピン棒で津島君の尻をさらに1発打つのだった。
「いっ、いてーーー!!」と、津島君は思わず叫び、反射的に短パンのケツをひいて、両手でケツをさする。
そのしぐさに、6Cの先輩たちは、さらに大笑い。
そんな中、津島君は、これ以上ケツピン棒で体育短パンのケツをバチバチ叩かれてはたまらんと思ったのか、先輩たちの笑い声に負けないような大きな声で、
「昨日、掃除中に、ダビデ像を壊しました!ごめんなさい!」
と言って、スポーツ刈りの頭をペコリと下げる。恥ずかしいのか、顔は耳まで真っ赤だった。
津島君の小学生とさして変わらなく聞こえる甲高い謝罪の声は、高校3年生の先輩たちにとって、まだまだかわいいひよっ子の声のように響いていた。そして、6Cの生徒たちは、自分たちの前に立つ津島君に、「コイツ、ちょっとイジってやるか!」とでもいいたげな視線を向けるのだった。
高3の先輩たちの視線が一斉に自分に集中し、ますます顔を紅潮させる津島君。中2では一番のやんちゃ坊主も、高校3年生の先輩というのはやはり怖い存在だったのである。
そんな津島君に、
「ダビデのチンチンで何してたんだ?」
「シコシコしてたのか?!」
「シコシコすんなら、自分のチンコでしろ!!」
と、5年半、男子校の飯を食ってきた高3の先輩らしい遠慮のない下品な野次が、次々に飛んでくる。
さすがの津島君も、そんな先輩たちの野次に、ますます恥ずかしくなり、首から上はもうゆでだこのように真っ赤になり、下を向いてしまうのだった。
野次や笑い声でますます騒がしくなる6Cの31名の生徒たちを、
「コラ!おまえら静かにせんか!!」
と怒鳴りつける黒岩先生。その一喝で、やっと静まり返る6C・31名の生徒たち。
そんな中、急に静まり返った教室に、ガラガラと扉が開く音が響き渡るのだった。 第一美術室の後方の扉が、ガラガラと音を立てつつゆっくりと開き始めていたのだ。黒岩先生、津島君、そして、6Cの生徒たち31名が一斉に扉の方に目を向ける。しかし、そこには誰も立っていないし、誰かが入ってくる様子もなかった。
しかし、床の方に目を向けると、半分くらい開いた第一美術室の後ろの扉の下の方から、他の生徒たちと同じく体操服を着た生徒が1名、匍匐前進で床を這うように教室に入ってくるのだった。
「コラ!!男だったら堂々と入ってこんか!!」
と、再び、黒岩先生の怒鳴り声。6Cからは大爆笑が起きる。
「はい!短パンを探していて遅刻しました!すいません!」
黒岩先生の怒鳴り声に、あわてて飛ぶように立ち上がり、直立不動の姿勢になり、津島君と同じようなスポーツ刈りの頭をペコリと下げる生徒。
「短パンが見つからなければ、ブリーフ一丁で来い!!」
と、再び、黒岩先生が怒鳴る。教室からは大爆笑だ。
「あっ・・・うちの主将だ・・・センコーにみつかって、なんか、かっこわりぃーな・・・」
その様子を黒板前に立たされて見ていた津島君は、そう思って再び下を向いてしまう。
5・6時間目の美術の授業に遅刻した生徒、すなわち、6C・32人目の生徒は、サッカー部主将の山岡勇(やまおか いさむ)君だった。そう、山岡君は、昨年、主将になったばかりの夏合宿で、津島君の後ろにつき、津島君の股間にしっかり性教育を施した「右手のひらの摩擦係数1.99999」の男だった。山岡君は、自分の体操服の白短パンをサッカー部の部室に置き忘れており、それを探していて、授業に7,8分ほど遅刻したのである。
「オレの授業に10分も遅刻するとは何事か!芸術を冒涜するにもほどがある!そこの壁に両手をついてケツを出せ!懲戒棒で指導してやる!!」
「えっ、10分も遅刻してないっスよ・・・」といった顔をしながらも、この「よっぱらい」とあだ名される、いつも酒の臭いプンプンの黒岩先生に逆らえばろくなことがないとわかっているのか、山岡君は、
「ィ〜ス!」
とだけ返事をし、特に黒岩先生に反抗する様子もなかった。
しかし、美術室を見回し、黒板の前に立たされているサッカー部の後輩・津島君の姿をみて、驚いたような顔をする。
「裕二!おまえ、なんでここにいるんだ?」
クラスから、再び、大爆笑が起きる。
「ィ〜ス!ダビデ・・・壊しました・・・」
津島君のその応答に、クラスはさらに大爆笑。
「おまえの後輩、ダビデのチンコ、こすり過ぎたらしいぜ!」
と誰かが言うと、もうクラスは爆笑の渦につつまれる。
それを聞いて、山岡先輩はうれしそうな顔をして、
「おお!そうか!よくやった!それでこそ、オレの後輩だ!オレも、中2のとき・・・」
と、自分自身がダビデのチンコを壊した時の武勇伝を後輩に披歴しようとする。
明和学園において、レプリカ・ダビデ君のチンコ脱落は、昨日今日始まった事件ではなかったのだ。第二次世界大戦前、旧制・明和中学校の時代から、そのペニスは、多くの生徒の右手でシコられ何度も壊されてきた、黒光りと脱落の歴史を持つ性教育用、もとい、美術教育用・レプリカ彫刻だったのだ。
「いい加減にしろ!!おまえらはどれだけ芸術を冒涜すれば気が済むのだ!山岡!ここへきて、早くケツを出せ!」
いつものように杖をついて教室の後方に来た黒岩先生は、右手にケツピン棒を持って、山岡君を待ち構えていた。
「えっ!後輩のみている前でケツピンっすか・・・」
と言うと、山岡君は、クラスの前ではめずらしく、恥ずかしそうな真っ赤な顔になるのだった。
津島君は、山岡先輩が自分の目の前で叱られて、ちょっとだけ気まずい気持ちになる。それでも、サッカー部ではいつもかっこよく、リスペクトしている山岡主将が、自分と同じく遅刻でケツピン指導を受けるなんて!山岡主将に対して今まで以上に親近感がわいてくると同時に、ちょっとだけ得した気持ちになる。サッカー部の同期の悪友たちに、主将がケツピン指導を受けたこと、そして、それを自分がみていたことを、早く話したい気分になってしまうのだった。
「山岡さん・・・ガンバレ・・・」
と思いながら、津島君は、下を向きながらも、チラッチラッと、自分が所属するサッカー部の主将の方をみるのだった。
その時の山岡君は、サッカー部の後輩である津島君の面前で、自分がケツピン指導を受けることによほど抵抗があったのか、
「先生・・・あとじゃ、ダメっすか?いまはケツピン、勘弁してくださいよ・・・」
と、めずらしく、泣き言のようなことまで言い始めるのだった。
「ダメだ!」と黒岩先生はきっぱり。
6Cの連中は、固唾をのんで、山岡君と黒岩先生のことを見守っている。
そして、津島君は下を向いたまま、
「チェッ・・・山岡さん、主将のくせに、なんか、かっこわりぃな・・・ケツピンが怖いのかよ・・・」
と思い始める。
そんな中、6Cの連中の一番後方に座っていた、髪をビシッと角刈りに決め、真っ黒に日焼けした生徒が立ち上がるのだった。それは、明和学園・第49代応援団長の河西弘(かさい ひろし)君であった。
そして、山岡君の方を向くと、両脚をやや開いて、両手は後ろに組み、デカい声で、
「オッス!!」
と挨拶する。
津島君は、聞き覚えがあるその挨拶に、「あっ、応援団の人だ・・・」と思い、顔を上げて河西君を見るのだった。河西君は、5月の大運動会で、応援団長の大役を無事果たしていたのだった。
河西君は、後ろに回していた右手を、口のところにもってきて、メガホンのように口にあてると、山岡君の方へ向けて、野太い低い声で、
「西女(にしじょ)のスカート下からめくれ!」
と、調子をつけて歌うように言うのだった。
河西君のそれを聞いた6Cの生徒たちは、ほとんどの生徒が、ニヤニヤしながら、やはり野太い声で、
「よぉ〜〜〜〜!!」
と調子をとる。すると、河西君が、
「明和(めいわ)のブリーフ上からめくれ!」
と、調子をつけて続けるのだった。
それを聞いた6Cの生徒たちは、みんな、少し照れくさそうな顔をして頬を赤らめつつも、手を打って大笑いし、
「よぉ!!団長、名調子!!」
と口々に言い、続けて、
「ケツめくれ!!」
「ケツめくれ!!」
「ケツめくれ!!」
「ケツめくれ!!」
と、手拍子を打ち鳴らしながら、囃し立てるのだった。
そのクラスの様子に、「やられたー」いった表情をみせる山岡君。
山岡君は、ついに決意したような顔つきになると、黒岩先生が待ち構える壁のところへ行く。そして、短パンを脱ぎ捨て、体操服の下は、白ブリーフ一丁となる。高校3年生である山岡君の白ブリーフにも、そのフロント部分には、中学生と同じく、油性の極太黒マジックで「6C 山岡」と、クラス名と苗字がオンネームされている。
下は白ブリ一丁となった山岡君は、「よし・・・」とつぶやくように言うと、ゴクリと生唾をのみ込み、穿いていた白ブリーフのバックの腰ゴムに両手の親指をかけ、グイと拡げるようにすると、それをゆっくりと下げ、サッカーで鍛えてプリッと盛り上がったケツの双丘の下のふもとのところまでブリーフの腰ゴムを持っていく。そう、白ブリのバックの腰ゴムに親指をかけ、河西君が歌った通り、白ブリを上からめくり下げたのだった。
そして、両脚をひろげて、両手を壁につくと、プリっと丸出しになったケツを後ろに突き出し、
「お世話になります!」
と、半ばやけになったように叫ぶのだった。
それを聞いた河西君は、満足そうに頷くと、
「よし!山岡!それでこそ男だ!ガンバレ!」
と、6Cのクラスメートたちと後輩の津島君の前で、プリッと剥き出しの生ケツを晒してケツピン指導に備えている山岡君に言うのだった。
もとより、河西君と山岡君は、中学校以来の親友である。また、河西君が、黒岩先生のケツピン指導に、賛同しているわけでもない。
応援団長で、明和学園一の熱血漢である河西君は、親友の山岡君が、後輩の津島君がみている前とはいえ、めずらしくケツピン指導を受けることを渋っているところを見て、
「山岡、男らしくねーぞ!遅刻したのはおめえがわりぃんだから、グズグズいってねぇーで、男だったら、さっさとケツを出しやがれ!!」
と思い、さらには、後輩の津島君が見ている前であるからこそ、ケツピン指導に際して、山岡君のような女々しい態度をとるならば、明和学園・最上級生の沽券(こけん)にかかわると思い、明和学園・応援団の名物応援歌「ケツピン哀歌」の「聞かせどころ(サビ)」を歌って、山岡君に潔よい「ケツめくり」を促したのである。
ちなみに、ここで「ケツめくれ」とは、「居直る」ことを意味する「穴(けつ)を捲(まく)る」ではなく、パンツを下ろして生ケツを出す意味である。これは、当時、黒岩先生のように、ケツピン指導で生ケツを叩く教師もいたからである。
また、「西女(にしじょ)」とは、西東京女学院(にしとうきょうじょがくいん)の略である。
西東京女学院は、国鉄・中央線・西荻窪(にしおぎくぼ)駅から徒歩約10分のところにある中高6年一貫制の女子校である。
西女(にしじょ)のロングスカートの制服は、中央線沿線の学校に通う男子生徒たちにとって「あの長さがかえって卑猥だ」と評判であり、国鉄・中央線・東中野駅が最寄り駅の明和学園の生徒たちにも一度はめっくてみたいと思わせる「人気」の制服だったのである。
もちろん、明和高校の生徒たちの「スクールカースト」でトップ層にのし上がるには、運動部や応援団に所属して活躍するだけでは不十分であり、西女(にしじょ)に彼女(ガールフレンド)がいて、西女(にしじょ)の学院祭「しらゆり祭」の「入場許可券」を友達の人数分だけ調達できることも必要だったことを付け加えておきたい。
「よし!懲戒棒10発だ!覚悟しろ!」
「えっ・・・」
「遅刻1分につき、懲戒棒1発!おまえは、本日、オレの授業に10分の遅刻をした。よって10発だ!」
と、冷酷に言い放つ黒岩先生。黒岩先生の酒臭い息が、壁に両手をついてケツを後ろへ突き出している山岡君の鼻を憑く。
「ちくしょー、このよっばらい・・・いつもそんなに叩かねークセに・・・今日に限って・・・」
山岡君はそう思うも、後輩の手前、もう女々しく抗議はできないと思うのだった。
「えっ・・・10発・・・」
山岡君に男らしくケツピン指導を受けるように促した河西君も、その回数を聞いて驚き、やや後悔するのだった。しかし、もう後へは引けないと、
「山岡、ガンバレ!負けるな!」
と応援する。
親友・河西君の応援に、山岡君は、
「オッス!」
と応えると、今一度、
「お世話になります!!」
と雄叫びを上げるのだった。
「フフフ・・・芸術を冒涜しおって・・・この棒でたっぷりとしつけてやるわ!!」
そういうと、黒岩先生は、左手で杖は床についたまま、右手に持った青ケツピン棒を振り上げ、それを山岡君の剥き出しのケツめがけて、思い切り振り下ろすのだった。
ブン!!
黒岩先生のケツピン棒が空を切る鈍い音がしたかと思うと、山岡君は剥き出しのケツにスゥと涼風を感じ、「くる!」と思わずギュッと両目をつむる。
ビシッ!!
山岡君の生ケツのど真ん中を容赦なく強襲する音が、美術室に響き渡るのだった。
ケツピン棒がケツに着地する時のあの焼けるような熱い痛さを知っている6Cの連中も、そして、津島君も、思わずギュッと目をつむる。
「お、お世話になりました・・・」
山岡君が絞り出すような声で挨拶をする。山岡君のプリっと剥き出しになったケツに、ケツピン棒によって描かれた赤い1本の罰線(ばっせん)がうっすらと横一文字についている。小麦色に日焼けしている山岡君。しかしそのケツペタは、ブリーフの日焼け痕がついたかのように白さが際立っており、その赤の罰線は、いやがうえにも鮮やかだった。
ケツがジリジリと焼けるように痛かった。壁についている両手で、すぐにでもケツをさすりたかった。しかし、後輩の津島君がみている手前、そんなことはできない。山岡君は、2発目の笞(ムチ)が振り下ろされるのを覚悟して、
「お世話になります!!」
と、2発目のケツピン指導を願い出るのだった。
「フフフ・・・いくぞ!!」
ブン!!
ビシッ!!
山岡君の白いプリケツのど真ん中、1発目と寸分たがわぬ位置に、2発目の笞(ムチ)が容赦なく噛みつく。
「いっ、いてぇーーー!」
と思わず叫んでしまう山岡君。しかし、親友・河西君が、
「山岡!!負けるな!!」
と、応援する。
河西君のその声に、山岡君は、あわてて、
「お、お世話なりました!」
と挨拶するのだった。
山岡君は、後ろに突き出したケツに、焼きたての餅が張り付いてしまったような熱く重い痛みを感じている。すぐにでもその熱い餅をケツから剥がしたい気持ちだった。しかし、壁に両手をついたまま、三発目を覚悟し、
「お世話になります!」
と絶叫するのだった。
その時、赤い太い線が入った山岡君のケツを眺めていた黒岩先生の顔から、獲物を狙うようなギラギラとニヤケた笑みがスゥと消える。そして、思わずギョッとして後ろを振り向き、廊下の方をみるのだった。
「おい、いま、そこの廊下を誰かが通ったか?」
と、黒岩先生は6Cの生徒たちに聞くのだった。
急におびえたような表情をみせる黒岩先生に、6Cの生徒たちは驚き、第一美術室の廊下側の窓の方を見る。しかし、そこには誰もいなかった・・・。
「このよっぱらい・・・今日は、特にあぶねぇーな・・・」
と、6Cの生徒たちは思うのだった。
黒岩先生は、まるで酔いから醒めたようなに、急に白けた顔になり、
「チッ!今日は、時間がねーから、2発でゆるしといてやる!もう二度と遅刻すんな!」
と、自分の前で生ケツを突き出している山岡君にそう言うのだった。
山岡君は、「助かった・・・」と言いそうなのをグッと堪えて、
「はい!お世話になりました!」
とデカい声で挨拶する。
黒岩先生は、
「よし!自分の席につけ!もう時間がない!デッサンを開始するぞ!」
と言うと、再び、杖をつきながら教壇の方へ戻っていく。
山岡君は、壁から両手を離すと、ブリーフのバックの腰ゴムに両手の親指をかけて腰ゴムをひろげ、腰ゴムがケツの皮膚をこすらないようにそぉ〜と慎重に、ケツの下までおろしてある白ブリーフを、腰のところまで上げるのだった。そして、
「ふぅ〜」
と、安心したように一息つくと、さっき床に放り投げた白短パンをひろい、やはりその腰ゴムがケツを擦らないように慎重に穿くのだった。
津島君は、そんな先輩の姿をみながら、
「山岡さん、部活ではすげーかっちょいいけど、ケツピン食らうとちょっとかっこわりぃよな・・・」
と思ってしまう。しかし、自分の視線が山岡先輩に気づかれそうにそうになると、サッと下を向いて、先輩と目があわないようにするのだった。
剥き出しのケツにケツピン指導2発を食らった山岡君は、己のケツをいたわるように白短パンのケツをそぉっとさすりながら、河西君の隣の席にそぉ〜と座るのだった。
何もなかったように、「よぉ!おまえの後輩、なかなかやるじゃん・・・」と山岡君に声をかける河西君。それに対して、やはり何もなかったように、顔にやんちゃ坊主の笑みを浮かべて「まあな・・・」と返す山岡君だった。
12 デッサンモデル
黒岩先生の気まぐれなケツピン指導にはもう慣れっこなのか、黒岩先生が教壇に戻るころには、6Cの生徒たちがいる第一美術室は、何もなかったように、ざわつき始めていた。
「コラ!静かにしろ!さきほども言ったように、今日はダビデ像は使用不可であるから、ダビデ像のデッサンの代わりに、ここに立っているチビをデッサンすることにする!」
教室から、再び、大爆笑がおきる。
「いいか、本日の人物デッサンであるが、おまえらは、自画像デッサンなどですでにその基礎は学んでいるはずだ。したがって、本日の課題は、その応用として・・・このチビのケツを鉛筆デッサンしてもらう。」
教室には、さらに大爆笑の渦がわき起こる。
「20分で1スケッチ、10分の休憩を挟み、さらに20分でもう1スケッチだ。最初のスケッチと2枚目のスケッチは、座る椅子の位置を変えて行う事。いいな!2枚提出できたものから、かえっていいぞ!」
6Cのクラスからは、
「ィ〜ス!」「はい!」「おーー、やりぃー!」
などの声があがる。
黒岩先生は、黒板の前、教壇の上の木製の台の上に立っている津島君に向かって、
「おい!チビ!黒板の方を向いて、短パンとパンツを下ろし、両脚を少しだけひらいて立て!」
と命令する。
クラスから、再び、笑い声が沸き起こるなか、津島君は、真っ赤な顔になりながら、
「はい・・・」
と返事をして、黒板の方を向くと、黒岩先生の命令通り、短パンとスクールブリーフを膝までおろすのだった。
今度は、クラスから大爆笑が起きる。津島君の白ブリーフに縁どられた日焼け痕のついた、かわいくぺローンと白いお尻の、ちょうどプリッと盛り上がった双丘の頂上あたりに、2本の赤い線がついていたのだ。もちろんそれは、今朝遅刻した罰として1発、そして、来週の遅刻分の罰の「前渡し」として1発、合計2発のケツピン指導を担任の吉川先生から昼のSTで頂戴した時にこしらえた罰線(ばっせん)であった。
サッカー部の山岡先輩が、さっきまでのきまり悪さを吹き飛ばすかのように、
「裕二!その赤い線はどうした?」
と野次を飛ばす。もちろん、6Cの連中からは大爆笑。
津島君は、再び、耳まで真っ赤になってしまう。しかし、津島君が、何か言おうとするのを遮るかのように、黒岩先生が、
「これはダビデ像を壊した罰を尻に受けたからだな!チビ!反省したか?」
と聞いてくるのだった。
クラスからは笑いが起きる。
津島君は、その時、吉川先生からは、レプリカ・ダビデ像のペニスを壊したことではケツピン指導を受けていないこと、そして、その日の昼のSTで、吉川先生にはめずらしく、ケツピン指導2発を宣言されたことを再考するのだった。そして、津島君は、吉川先生の「顔をたてる」ために、
「はい・・・イエローカード・・・あっ、吉川先生からケツピン2発、もらいました・・・ごめんなさい、反省してます・・・」
と言うのだった。
6Cからは、笑い声に交って
「おーーー!」
と、賞賛の声あがる。高3の先輩たちの賞賛の声を聞いて、津島君はちょっと誇らしい気持ちになるのだった。
後輩のかわいいケツに刻印された赤い罰線(ばっせん)2本をみて、山岡君と河西君は、
「イエローカードのケツピンか・・・最近、くらってねーけど、中学の頃は、よくやられたよな・・」
「そうそう、パンツ一丁のケツよくやられたよな・・・けっこう、いてぇーんだよな・・・」
と言いながら、中学生の頃のほろ苦い経験を思い出したかのようにポッと頬を赤らめるのだった。
黒岩先生は、騒がしくなってきたクラスを鎮めるかのように、咳ばらいをして、
「よし!デッサンはじめ!」
と宣言する。
しかし、山岡君は、さらに後輩のことをからかってやろうと思い、スクと手を挙げ、
「先生!キンタマも描いていいんですか!?」
とニヤニヤしながら質問するのだった。
クラスからは大爆笑。
黒岩先生のカミナリが再びクラスに落ちるかと思いきや、やけにまじめな顔になって、
「よし!いい質問だ!」
というのだった。
先生のカミナリを予想していた6Cの連中は、ちょっと拍子抜け。
「おーーー!」
と、賞賛の声が上がる。それを聞いて、山岡君は、「どうだ、裕二、聞いたか、さすがおまえの先輩だろ・・・」とでもいいたげに、得意そうな表情を浮かべるのだった。
黒岩先生は、完全に酔いから醒めたかのように、生き生きとした表情になり、
「では、オレから質問する!おまえの位置から、モデルのキンタマは見えるか?」
と、山岡君にまじめな声色で質問してくるのだった。
山岡君は、「えっ・・・」と思い、上体を河西君の方へ傾けて、サッカー部のかわいい後輩・津島君のケツの下、少しだけひらいた両ふとももの間をのぞこうとする。
「バカモン!!上体は動かすな!!まっすぐに座って見るのだ!」と黒岩先生が一喝する。
「は、はい・・・」
山岡君は、姿勢をもとに戻して、津島君の左右両ケツペタの下をみるのだった。しかし、山岡君の座っている位置からは、津島君の左太ももが遮って、津島君の両足の間にぶらさがるタマタマを裏からみることはできなかった。
「えーと、みえません・・・」
と、山岡君は、姿勢をまっすぐにして見たままを答える。
黒岩先生は、満足そうに頷くと、
「よし!だったら、キンタマを描いてはいけない!」
と答えるのだった。そして、今度は、
「では、その隣のヤツ、おまえはどうだ?モデルのキンタマはみえるか?」
と、河西君に聞いてくるのだった。
「えっ・・・自分の位置からは、半分くらいみえます・・・」
と、河西君が答える。クラスからは笑い声が起こる。
黒岩先生は、再び、満足そうに頷くと、
「よし!キンタマが半分見えるのであれば、それを見えたままに描くこと!それが芸術だ!」
と、やけに堂々と答えるのだった。
それに別の生徒が、
「先生!ケツの赤い線も描いていいんですか?」
と質問する。クラスからは大爆笑。
「もちろんだ!お前らの位置からモデルのケツについた赤い線がみえるのであれば、赤鉛筆は使ってはダメだが、鉛筆で見たままに描け!」
と、黒岩先生はその生徒の質問に真剣に答えるのだった。
「おーーー!」
と、クラスからは賞賛の声が上がる。
「いいか、この教室でおまえらが座っている位置は、一人一人異なる。よって、おまえらが提出するデッサン画も、一人一人異なるはずだ!隣のヤツのを写したりしてもすぐにわかるからな!他人のデッサンを写したヤツは、カンニングとみなす!懲戒棒くらいではすまんぞ!上手下手は問わん!己の芸術に真摯に取り組むこと、いいな!では、デッサン始め!」
と、黒岩先生は高らかに誇らしげに宣言するのだった。
「はい!」
6Cの生徒たちのおケツ・デッサンが始まる。もちろん、その間、津島君は、モデルとして動けないことのつらさをヒシヒシと味わうのだった。津島君が楽しみにしていた2A・2B合同の体育授業でのサッカーの試合を「見学」扱いにして、レプリカ・ダビデ君の代打モデルをさせたのは、黒岩先生と吉川先生が前日に話し合って決めた、津島君へのお仕置きだったのである。
後日、6Cの生徒たちの作品は、職員室前の生徒作品用の掲示板にズラッと張り出され、多くの生徒や先生方がニヤケ顔で観賞していったという話ではある。
13 美術準備室の闇
デッサンの授業も6時間目に入ると、2枚目のおケツ・デッサンを仕上げた6C生徒たちが、クラス、出席番号、イーゼルナンバー、氏名を記して、教卓の上に置いて、第一美術室を出ていくのだった。
サッカー部の山岡先輩も、
「裕二、おつかれ!今日の部活さぼんじゃねーぞ!」
と、津島君に声をかけ、自分の作品を教卓の上に提出して、第一美術室から出ていく。
6Cの先輩たちが一人、また一人と、第一美術室からいなくなり、やけに教室がヒンヤリとしてくる。津島君は、急に心細くなり、左右、そして、後ろを見回すのだった。
津島君の後ろには、32台のイーゼルと誰も座っていない32脚の木製の椅子が残されている。そして、教室後方の壁に寄りかかるように立っている黒岩先生が、津島君の丸出しの尻をジッとみつめている。津島君がケツに感じていた視線は、すでに6Cの先輩たちのものではなく、黒岩先生の視線だったのだ。
「あ、あの・・・パンツと短パンはいていいですか?ちょっと寒いんですけど・・・」
季節は初夏。外はカラッとした梅雨前の6月の暑さだったが、第一美術室はやけにヒンヤリとしていて、津島君は、背中にゾクッとするような寒気を感じるのだった。
「おお、はいていいぞ!」
「あ、ありがとうございます・・・」
津島君は、急いでスクールパンツと体育短パンを上げて、デッサンモデル用の台と教壇から降りるのだった。
「おい、チビ、行儀よくモデルをした褒美をやるから、ちょっと、オレの部屋に来い・・・」
と、黒岩先生は言うのだった。
それを聞いた津島君は、その場から逃げたい衝動に駆られる。
第一美術室の後ろに掛かった時計をみると、6時間目の授業は、まだ30分近く残っている。今から、校庭に急げば、体育の授業のサッカーの試合に参加させてもらえるかもしれない。そんなことも考える津島君だった。
そんな津島君を逃がさないようにするためか、黒岩先生が津島君の後ろから、やけにやさしく、津島君の肩に右腕を回してくるのだった。その右手には、さっき山岡先輩の生ケツに容赦なく噛みついた青いケツピン棒が握られている。その時の津島君なら、それを振り切って、逃げることができたかもしれなかった。しかし、津島君は、黒岩先生のその毛深い右腕に無言の圧力のようなものを感じ、身体が固まってしまっていたのだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
校庭で行われている2A対2Bのサッカーの試合。ホイッスルを首から下げて、それを見守っている吉川先生。校庭の向こう側に、体育館の方から戻ってくる6Cの生徒たちの姿も目に入ってくる。
「おっ、カンカン(黒岩先生のこと)の授業が終わったのか・・・チビスケ(津島君のこと)のヤツも戻ってくるかな・・・フフフ、アイツ、どんな顔して戻ってくるか楽しみだな・・・ちょっとお灸がキツかったか・・・まあ、反省しているようだったら、サッカーの試合に参加させてやってもいいがな・・・」
と思う吉川先生。しかし、津島君が体育館の方から戻ってくることはなかった。
少し心配になった吉川先生は、自分が顧問をつとめるサッカー部の山岡君が戻ってくる姿をみつけ、
「おい!山岡!津島はどうした?」
と聞くのだった。
「ちわッス!裕二ですか?まだ美術室じゃないっスか・・・」
「もう授業は終わったんだろ?」
「ええ、6Cのヤツはもう誰も美術室にはいないと思いますよ・・・オレらが最後でしたから・・・」
「そうか・・・」
吉川先生の顔が急に曇るのだった。
「山岡!悪いが、オレと一緒に第一美術室へ戻ってくれ!」
「えっ、いいッスけど・・・でも、先生、体育の授業はどうするんですか?」
「それは辻岡先生に頼むことに・・・河西、悪いが、職員室に行って辻岡先生を呼んできてくれ、オレが、至急、美術室へいくことになったから授業の最後を頼みます、といえばすぐにわかるはずだ!頼むぞ!」
「オ、オッス!」
吉川先生の依頼に驚いたような顔をするも、吉川先生のただならぬ雰囲気に、吉川先生の頼みを快諾する応援団長の河西君だった。
「よし!山岡、来てくれ!」
「は、はい・・・」
吉川先生の態度に、山岡君も不安そうな顔つきをして、体育館の向こう側、第一美術室のある芸術科校舎の方へ向かうのだった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「遠慮なく入っていいんだぞ・・・さあ、入れ!」
気持ち悪いほどのやさしい声が、津島君の背後から聞こえてくる。黒岩先生は、津島君の真後ろに立ち、第一美術室の隣にある「美術準備室」と表札がかかった部屋のドアを開けるのだった。
「うっ・・・くっせぇ・・・」
黒岩先生に後ろから押されるようにして美術準備室に入る津島君。黒岩先生の酒臭い息と、部屋に充満するタバコ臭、そして、やはり部屋に充満する汗と脂が混じったような臭いに、思わず鼻をつまみたくなる津島君。
その部屋は、「美術準備室」とは名ばかりで、黒岩先生のねぐらになっているらしく、小さな机の上にはタバコの吸い殻が山盛りになった灰皿が置かれており、床には空の一升瓶が何本も置かれている。さらには、薄汚れたシーツが敷かれたベッドもあった。唯一、「美術」らしいものといえば、第一美術室に置かれていたのと同じ型のイーゼルが1台と、そのイーゼルに置かれた幕がかけられた油絵のキャンバスらしきものであった。
「さあ、入れ、入れ・・・タバコでも吸うか?それとも、酒でも飲むか?ワハハハ!」
授業の時とは打って変わった態度の黒岩先生。その薄気味の悪さに、急に不安になる津島君。ここは何とかして逃げなければと思うのだった。
「い、いいです・・・あの・・・帰っていいですか・・・た、体育の授業が・・・」
「フフフ、このチビめ、何をビクビクしているんだ・・・モデルになった褒美をやろうと言っているんだ・・・さあ、こっちへ来て、その絵の前に立ちなさい・・・」
「絵って、あれですか?」
津島君は、部屋に置かれたイーゼルに置かれた油絵のキャンバスらしきものを指さすのだった。
「ほう、よくわかったな・・・チビのクセになかなか目先の利くヤツだ・・・わかっているなら、早くその絵の前に立ちなさい・・・」
「は、はい・・・」
不安な表情でイーゼルの前に立つ津島君。そんな津島君の逃げ道を塞ぐかのように、津島君の真後ろに立つ黒岩先生。
「さあ、これから、オレの宝をみせてやるから、よーくみるんだぞ・・・フフフ」
というと、津島君の背後から、黒岩先生の毛深い右手がヌッと伸びてくる。そして、黒岩先生のその手は、津島君の前にある油絵のキャンバスにかかった幕をサッと払いのけるのだった。
「あっ!!あぁ・・・あーーーー!」
その絵を見た津島君は、股間をツーンと襲う熱い衝撃に、体育短パンの股間を両手で押さえて、その場にしゃがみこんでしまうのだった。
「コラ!!このクソガキ!!漏らしやがったな!!芸術を冒涜しおって!!さあ、立て!立って、短パンとパンツを下ろすんだ!!」
急に津島君を怒鳴る黒岩先生。
「ご、ごめんなさい・・・わざとじゃないです・・・ご、ごめんなさい・・・」
津島君は、泣きそうな声でそう謝りながら、どうにか立ち上がる。白短パンの股間は両手で隠すように押えている。体育短パンの前の部分には、透明の染みがにじんできていた。
「お前がSamen(ザーメン、ドイツ語で精液の意)を漏らしたことはわかっとるぞ!!下品なヤツめ!!これからこの懲戒棒で、たっぷり折檻してやるから、さあ、ケツを出すんだ!!」
津島君の後ろでそう言って怒鳴る黒岩先生は、津島君の短パンと白ブリーフの腰ゴムをわしづかみにすると、それをグイっと下ろそうとする。
「や、やめろ・・・わざとじゃないっていってるだろ!や、やめろ!!」
と抵抗する津島君。
「オラァ!往生際の悪い、ガキだ・・・オレに逆らうことなどできんぞ!!」
そう言って、黒岩先生は、グイグイと津島君の短パンと白ブリーフをまとめて下ろそうとする。津島君は、己の体育短パンと白ブリーフのフロント部分の腰ゴムを必死でつかみ、それに必死で抗(あらが)おうとする。
「やめろっていってるだろ・・・グスン・・・や、やめて・・・わざとじゃないから・・・やめてください・・・」
津島君の声が、だんだんベソかき声になってくるのだった。津島君がどう抵抗しても、大柄な黒岩先生の力に逆らうことはできなかった。
「わざとじゃないです・・・やめてください・・・あーーー」
ズズッ!!プリッ!!
果たして、黒岩先生の力が勝り、哀しいかな、津島君の白の体育短パンと白ブリーフは、ズズッと膝下まで一気にズリ下げられたのである。たらーっと透明な粘液が、津島君の股間から白ブリーフの中へと糸を引いている。あたりに、栗の花の青臭い匂いが漂うのだった・・・。
「ご、ごめんんさい・・・グスン・・・わざとやったんじゃないです・・・ごめんさない・・・・」
必死であやまる津島君。しかし、黒岩先生は、右手に再びあの青いケツピン棒を握りしめ、それを天井に向けるかのように高く振り上げるのだった。
「覚悟しろ・・・下品な悪ガキめ・・・これからたっぷりと折檻してやる・・・まずは、その赤い線がついた部分からだな・・・フフフ」
しかし、ケツピン棒を振り上げた黒岩先生は、ギョッとして後ろを振り向くのだった。しかし、美術準備室のドアのところには誰もいない。安心したような顔に戻り、再び、津島君のプリッとした生ケツの、昼のケツピン指導でついた赤い線に狙いを定める。
「フフフ・・・覚悟しろ、このクソガキめ!!」
「く、くる・・・」
ケツピン棒が飛んでくることを己のケツにビンビンに感じて、ケツに鳥肌が立ち、両掌をグッと握りしめ、奥歯を食いしばり、両目をギュッと瞑る津島君。そして、振り上げた笞を、津島君のケツめがけて、思い切り振り下ろそうとする黒岩先生。
その時だった、美術準備室のドアが、ガバッと開いて、
「その子の尻を打ってはならん!!その子の尻を打つことをわしは絶対に許さん!!すぐにやめい!!」
と、ド迫力の声が、黒岩先生を一喝したのだった。黒岩先生も、そして、津島君も、驚いて後ろを振り向く。
果たして、美術準備室のドアのところに立っていたのは、芸術科・主任教諭の村田兼良(むらた かねよし)先生だった。村田先生は、慶応3年生まれの92歳。中1の美術史のみ担当で、明和学園では最長老のおじいちゃん先生だ。あだ名は「じっちゃん」。100点満点であるはすの定期試験では、200点の配点をして、生徒たちに「ゲタ」をはかせてくれる、奈良の大仏級に大甘の仏の先生だった。
しかし、その日の村田先生は、鬼の形相で、黒岩先生のことを睨みつけている。そして、右手には、ケツピン棒を握りしめていたのだ。ケツピン棒に、ビニールテープは巻かれておらず、ケツピン棒カラーは、ナチュラル・バンブー・カラーだった。
「ひぇ〜〜〜、お師匠様、こ、今回だけは、お、お許しください・・・」
「たわけ者!!今回で何回目だと心得ておる!!しばらくおとなしくしていると思っておったら、また、悪いクセを出しおったな・・・今日という今日は絶対にゆるさんぞ!!うえさま(徳川慶喜のこと)に代わり、この懲戒棒で、百叩きにしてやるわ!!」
「ひぇ〜〜〜、それだけはどうかお許しを・・・」
黒岩先生は、崩れるように、美術準備室の床に座り込むと、村田先生の方に向かって、土下座をするように頭を下げるだのった。
そのすきに、体育短パンとパンツをサッと上げて、村田先生の後ろへと逃げてくる津島君。
「よしよし・・・もう心配はいらんぞ、そなたは、ちぃと部屋の外に出ていなさい!」
と、やさしくも、凛とした声色で、津島君に指示する村田先生。
「は、はい・・・」
そう返事をして、廊下に出てきた津島君に、
「裕二!!大丈夫か!」
「チビスケ!!」
と、駆けつけてきた吉川先生と山岡先生が声をかけるのだった。
その二人の姿をみて、急に安心したのか、津島君の目には急に涙があふれてくる。それを右腕で必死になってふき取ろうとする津島君。そして、二人の方をむき、黙ってコクリと頷くのだった。
「お、お許しを、もう二度といたしませんので、懲戒棒だけはお許しを・・・」
美術準備室の中から聞こえてくる黒岩先生の許しを乞う情けない声。そして、土下座する黒岩先生の前に鬼の形相で立つ村田兼良先生。
「ならん!!この不心得者めが!!御父上が遺された、至高の芸術作品を、かくのごとき下品な目的に使いおるとは!!芸術を冒涜しておるのは、ほかならぬ、そなたじゃ!!許さん!!この懲戒棒で、百叩きと申したはず!!さあ、明和中学を卒業した益荒男ならば、潔く、尻を出すのじゃ!!」
村田先生のその姿と、そのもの言いに、津島君も、山岡君も、吉川先生も、
「じっちゃん、こえー(怖いの意)。」
「じっちゃん、こえー。」
「じっちゃん、こえー。」
と、つぶやくように言うのだった。
そして、村田先生と黒岩先生の二人のやりとりに、吉川先生は、ニヤニヤしながら、
「まあ、芸術科の教務のことは、お二人でどうぞごゆっくり・・・」
と言って、美術準備室のドアをそぉっと閉じるのだった。
「ひぇ〜〜〜、お許しを・・・二度と、いたしません・・・折檻だけはご勘弁を・・・」
と、黒岩先生の泣くような声が部屋の中から響いてくる。そして、
ベチ!ベチ!ベチ〜〜〜ン!!
と、竹の笞が黒岩先生の尻を打つ音が聞こえてくる。
「さあ、尻をしっかりとめくらっしゃい!!」
「ひぇ〜〜、後生でございます・・・ブリーフを下ろすことだけはお許しを・・・」
「往生際が悪い!!明和の懲戒棒は、剥き出しの尻に受けてこそ、効果があるのじゃ!その白い布がじゃまじゃ!!尻をしっかりめくるのじゃ!!」
ベチ!ベチ!ベチ〜〜〜ン!!
「ひぇ〜〜、お許しを・・・もういたしません・・・」
その日、黒岩先生が村田先生からケツピン棒で何発、折檻されたかは定かではないが、おフランスに留学経験のある黒岩先生は、越中ふんどし世代ではあったが、ブリーフが下着として機能的であることを知っており、明和学園・購買部で高校生用のスクールブリーフを購入しては穿いていたという話である。ちなみに、黒岩先生の購買部でのブリーフ・ショッピングは、すべて師匠である村田先生の付け買いとなっており、そのこともあとでバレてしまい、激怒した村田先生から、再び、みっちりケツピン指導を受けたとのうわさである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
村田先生のケツピン棒が黒岩先生のケツを打つ音と、黒岩先生の悲鳴が聞こえてくる美術準備室をあとに、吉川先生と山岡君は、芸術科校舎から出ようとする。そして、その後を、津島君が下をむいたまま、トボトボとついていくのだった。
「あ、あの・・・ボ、ボク・・・わざとじゃないんです・・・ごめんなさい・・・」
津島君のいつになく神妙なその声に、吉川先生と山岡君が後ろを振り向く。津島君は、体育短パンのフロント部分にべっとりと染み出てきたクリーム色のネチョ〜とした粘液を両手で隠そうとしている。それをみた吉川先生も山岡君も苦笑い。
吉川先生は、ポンと軽く山岡君の背中を叩くと、
「じゃあ、あとはサッカー部同士ってことでうまくやれよ・・・今日はミーティングだからな・・・遅れるなよ!」
といって、先に歩いて行ってしまうのだった。
吉川先生が行ってしまうと、山岡君は津島君の方を向くと、
「さあ、早く、これで拭けよ!拭いたら、今日、美術準備室であったことは、全部、忘れるんだ!いいな!」
といって、山岡君は、体育短パンの尻ポケットに丸めてつっこんであった白手拭(てぬぐい)を出して、津島君に渡すのだった。
それは、校則違反の「腰手拭」をするためのものであった。戦前、旧制高校の生徒が好んでやっていた学ランの腰から手拭をぶら下げる「腰手拭」が、懐古趣味的に、当時の男子高校生たちの間で流行していたのだ。もちろん、明和学園では、バンカラ過ぎるとして禁止されており、みつかれば、ケツピン指導が待っていたのである。
「あ、ありがとうございます。」
といって、その手拭を受け取る津島君。
「短パンを着替えたかったら、保健室にいって借りろよな!」
といって、ニヤリと笑う山岡君。
「えっ!あれはいいです。部活のサッカー短パンがあるからそれに穿き替えます!」
と、真っ赤な顔になって、あわてて言う津島君。
中1の時、体育の時間にケガをして血がついてしまった短パンを、保健室で予備の体育短パンに着替えたところ、尻ポケットの部分に赤い糸で、大きく「保健室備品」と刺繍がほどこされており、クラスに戻って、「やーい!!おもらし裕二!!ウンコでも漏らしたのか!?」とからかわれてしまったのである。それ以来、保健室の備品にはこりごりの津島君だったのである。
「ハハハハ!たしかにあの短パンとパンツは、まずいよな!」
と笑う、山岡先輩。
そんな山岡先輩を、ちょっと不安そうな表情でみつめる津島君。そんな津島君に、
「バーカ・・・心配すんな・・・お前があの絵をみてチンコがビンビンになって、ドピュドピュってもらしちまったこと、誰にもいわねーから・・・男があんな卑猥な絵をみせらたら、誰だって、ああなるんだ・・・」
といって、山岡先輩も経験があるのか、ポッと頬を紅潮させるのだった。
「山岡さんも見たんですか?あの絵・・・」
「あ、ああ・・・中学の時にな・・・」
それを聞いて、ちょっと安心した表情になる津島君。山岡先輩は、中腰になって、津島君と目線の高さをあわせると、小声で、
「そんなことどーでもいいから、今日のことは全部忘れろ・・・それから・・・オレもお前があの絵をみてアレ漏らしちゃったこと、誰にも言わねーから、おまえも、オレがよっぱらいの美術の時間に遅刻して、ケツピン食らってケツさすってただなんて、サッカー部の連中に絶対言うんじゃねーぞ!!高3にもなってケツピン食らってケツさすってんじゃ、主将としての立場ねーからな・・・いいか?」
「は、はい!」
津島君はニヤッとした笑みを浮かべて、元気に返事をする。山岡先輩は、右手で、津島君のスポーツ刈りの頭をやや乱暴に撫でると、
「よし!これは男同士の約束だからな!」
というのだった。
「はい!」
「よし!じゃあ、早く体育館の便所で短パンとパンツの汚したところ拭いて来い!!」
「はい!」
津島君は、元気に返事をして、体育館棟の中へと走っていく。山岡君は、後輩の後ろ姿にやはりチビだった自分自身の中学時代の面影をみて、苦笑いするのだった。
13 堕教師・黒岩の最期
1959年(昭和34年)12月下旬のある日の早朝。学園・用務員の田島さんが、美術準備室のベッドの上で冷たくなった黒岩先生をみつけ、あわてて、冬期休暇中に登校中の宿直教師に報告し、警察と救急に連絡がなされた。警察に引き取られた黒岩先生の遺体は司法解剖にふされ、死因は「重度のアルコール性肝炎を起因とする急性多臓器不全」と鑑定診断された。
学園・用務員の田島さんの話だと、遺体発見時、美術準備室には、ベッド以外は何もおかれておらず、イーゼルに置かれれていたあの絵もイーゼルごとなかったということである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
翌年の1月。3学期の始業式の校長訓話を終えて、校長室に戻ってきた松平校長のことを、芸術科・主任教諭の村田兼良(むらた かねよし)先生(93歳)(中1の美術史のみ担当)が待っていた。
校長室のソファの上にちょこんと腰を下ろす和服姿の村田先生。松平校長(60歳)が部屋に入ってきても、立ち上がることはせず、
「やあ、校長先生、始業式の方ごくろうでしたな。」
とだけ言うのだった。
「いやいや、村田先生・・・お待たせしました・・・校長訓話が、いつになく、長くなりましてな・・・ワハハハハ!!」
そういうと、松平校長は、村田先生がちょこんと座っているソファとはテーブルを挟んで反対側の下座のソファに腰を下ろすのだった。校長先生と村田先生が相対して座るその間のテーブルの上には、茶色い封筒と白い布に覆われた油絵のキャンバスのようなものが置かれていた。
「校長先生、この度の黒岩のことは、誠に申し訳なかった・・・芸術科主任として責任を感じております・・・わしが、戦争から戻ってきた彼奴(きゃつ)を美術準備室に住まわせたのが、そもそもの間違いだったと・・・」
そう言って白髪の頭をペコリと下げる村田先生。
「いえいえ、先生の責任などとは、めっそうもない・・・どうか、頭をお上げください・・・」
と、松平校長。
「いや、校長であるそなたにそう言ってもらえると、ありがたい・・・わしも少しは気持ちが楽になりますぞ・・・」
と、村田先生。
「ところで、これが黒岩の遺書と遺品です。遺書には、自分には家族も親族も残っていないから、この絵は明和学園に遺贈したいと書いてある・・・。校長先生、いかがいたしますかな?」
そう続けて言う村田先生に、松平校長は、
「では、ちょっと失礼して・・・」
と言って、テーブルの上に置かれた茶色い封筒を手に取り、その中に入った、一枚の便箋を取り出し、読むのだった。
「フムフム・・・これは、黒岩先生の筆跡に間違いないようですな・・・」
つぶやくようにそうに言うと、松平校長は、テーブルの上におかれた油絵のキャンバスのようなものの上を覆う白い布をめくるのだった。
「おっ・・・こ、これは・・・」
「そうじゃ、彼奴(きゃつ)は、その裸婦(らふ)画を、小柄な中学の生徒にみせては、その反応を観察して楽しんでおったのじゃ・・・」
そういうと、村田先生は、なんとも悲しげな表情をその皺が深く刻まれた顔に浮かべるのだった。
「しかし、村田先生、この絵は、昭和19年に警察に押収されたのではありませんか?」
「当初はわしもそう思っておったんじゃがな・・・」
そう言うと、村田先生は、戦争中の苦々しい出来事を思い出すように語り始めるのだった。
それは昭和19年の春。
陸軍省が、黒岩先生の父親であり、日本画家として当時高名だった黒岩幹治(くろいわ かんじ)画伯に、戦意高揚のために少年雑誌の表紙絵を描くように依頼するのだが、明治生まれ硬骨漢だった黒岩画伯は、「わしに少年雑誌の画を依頼するなど、失礼千万!そもそもわしは、英米との戦争には絶対反対じゃ!!」と一蹴してしまうのだった。
軍部にたてついて、ただで済む時代ではなかった。時をおかずして、警察が、黒岩画伯のアトリエを強制捜査し、画伯の作品をすべて押収してしまうのだった。当時、警察は、黒岩画伯のことを「婦女の裸体の絵ばかりを描く、時節にそぐわないけしからん絵師」としてマークしており、「戦争に反対じゃ」と言い放ったという密告情報は警察に取り締まりのための絶好の機会を与えてしまったのだ。
黒岩画伯は、逮捕され、取調室で殴る蹴るの暴行をうけた末、「わいせつ物陳列の罪」で起訴され裁判にかけられ、あれよあれよいう間に、有罪判決を受け、帝都・中野にあった豊多摩(とよたま)監獄に収監されてしまう。豊多摩監獄は、第二次世界大戦前、いわゆる思想犯を収監する刑務所として悪名高い行刑施設であった。
「黒岩先生が徴兵されたのは、いつごろでしたかね?」
「ふむ、あれは昭和19年の末だったはずじゃ・・・三十路を過ぎた教員が兵隊にとられるなど、当時としても稀有なことじゃった・・・御父上が刑務所に入れられたことが影響していると、うわさになったものじゃ・・・」
「ええ、私も校長として、大いに驚かされました・・・」
「入隊の前日、彼奴(きゃつ)がわしのところに訪ねてきてのぉ・・・いま、ここに置いてある画をわしに預かってほしいと言うてきおったのじゃ・・・」
「なんと・・・」
「わしもこの画をみて驚き、彼奴(きゃつ)に質したところ、この裸婦の画は、御父上がパリの高級娼婦をモデルにして描いたもので、朝と夕、2対の画だというのじゃ、そして、警察が押収したのは、2対のうちの一つである『窓辺の裸婦〜ルベヂュソレイ〜』だというのじゃ・・・」
「ルベヂュソレイ」とはフランス語で lever du soleil と綴り、サンライズ、すなわち、日の出の意味である。
「では、ここにある絵は、夕方の方ですか・・・」
「そうじゃ、『窓辺の裸婦〜クセヂュソレイ〜』じゃ・・・」
「クセヂュソレイ」とは、なんかプンプン臭ってきそうな響きがあるが、さにあらず、フランス語では coucher de soleil と綴り、サンセット、すなわち、日没の意味である。
村田先生の話を聞いて、あらめて、その絵を見る松平校長。
自分の目の前に置かれた油絵は、窓辺に置かれた椅子に座って、大きく両脚を開き、己の恥部を露わにしている裸婦の姿であり、背後の窓には、水平線に沈む太陽が描かれている西洋画であった。しかし、着目すべきはその構図ではなく、そこに描かれた女性の恥部が、油絵とは思えないほど、精緻に描かれていることだった。それには、60歳になる松平校長も目を見張り、年甲斐もなく股間に春の疼きを感じてしまうほどエロい女性のヌ―ド画だった。
「フムフム・・・なんと卑猥な・・・西洋のよたか(娼婦のこと)とは、かくも下品に股をひろげるものなのか・・・これならば、軍部の影響を受けた裁判官でないわたしであっても、わいせつと判断するに違いない・・・」
と、松平校長は思うのだった。
「彼奴(きゃつ)は、その後、陸軍二等兵として、ビルマ戦線に送られおった・・・」
「ええ、それも噂に聞きました・・・」
「終戦後、命からがら戦地から戻ってくるも、御父上は獄死し、ご母堂は3月の東京大空襲でお亡くなりになったそうな・・・それで、彼奴(きゃつ)はわしを頼ってやってきて・・・仕方なく、あの美術準備室を、彼奴(きゃつ)の当面の住処としてあてがったのじゃ・・・昔のように、明るく快活な教員として、明和の生徒らに美術を教えてくれるものとばかり思っておうた・・・しかし、彼奴(きゃつ)は人が変わってしもうた・・・戦(いくさ)が彼奴(きゃつ)の性根をゆがめてしもうたのじゃ・・・」
「先生のお気持ちは、重々・・・」
「いや、いささか話が過ぎたようじゃ・・・年寄の独り言じゃ、忘れてほしい・・・ところで、どうじゃな、この画を受け取っていただけるかな?」
「そうですな・・・黒岩先生のご遺志は重々ありがたいのですが・・・思春期の男子生徒の学び舎の備品として、果たして、この絵はいかがなものでしょうか?」
「フォフォフォ・・・校長は、この絵をわいせつであると思われたのじゃな・・・」
「いや、決して、そういうわけでは・・・」
「黒岩画伯の裸婦画は、いまでも、英米では高い評価を受けておりますぞ・・・米国のボストンの美術館では、黒岩画伯がパリ時代に描き現地に残してきた油絵のコレクションがあり、たいそうな評判なそうじゃ・・・」
「なんと、そうなのですか・・・・」
驚いたような表情をみせる松平校長のことをスルーするかのように、村田先生は、話しを変えるのだった。
「時に校長、オリムピックがこの日本で開かれるとは、10年前には夢にも思いませんでしたな・・・」
「おっしゃる通りで・・・」
「オリムピックが終われば、この日本も大きく変わっていくでしょうな・・・その頃には、この木造校舎も陳腐になり、最新設備を持った新校舎へ建て替えようという話が持ち上がるかもしれない・・・大枚(たいまい)がかかりますぞ、寄付ではまかなえんほどのな・・・フォフォフォ」
その話に、松平校長の目がギラりと光るのだった。
「・・・・それでは、村田先生、黒岩先生のご遺志もあることですし、明和学園がこの絵をいただくかは理事会にかけてからということにして、いましばらくは、一応お預かりするということで、いかがでしょうか?」
「フォフォフォ・・・一応預かり置くとは・・・なかなか深い言葉じゃ・・・さすが、お役人出身の校長先生ですな・・・いや、誠に深い・・・フォフォフォ」
その後、明和学園の理事会で、この絵のことが議題に上がったことは一度もなかったという・・・。
このページの先頭に戻る / 南寮編・目次に戻る / 南寮編・スピンオフの目次に戻る